|
|
|
|
| |
 |
| ●丸田藤左衛門生家 |
文化2年(1805)10月10日込之上に生まれる。通称藤左衛門、後監物と改める。少壮時郷人森重蔵に撃剣・柔道を学ぶ。嘉永元年(1848)新宮藩が新法を設け、十津川郷の移出木材に対し高い口銀を課したが、郷中総代として紀州藩に対して廃止運動を行なった。幕末米艦来航し天下騒然たる時、郷中59ケ村の総代を集め、村々に十匁銃・陣笠・カルサン袴等を購入することとし、他日の用に備えた。又大阪から萩野正親を招き、萩野流の砲術を学び、一子藤助や郷人等を激励して武事を銃練した。現在歴史民俗資料館には、この時の大砲模型や兵法書が保存されている。安政4年(1857)丹波亀山の藩士長沢俊平や郷士達と相計り、郷中の勤皇思想を鼓舞するため、滝峠に護良親王御詠の碑を建立した。5年(1858)正月上平主税・深瀬繁理・野崎主計等と上京、梅田雲浜・長州藩の宍戸黒九郎兵衛等に面会、長州と十津川の物産交易と称し、その実国事を密に論議した。4月同志と共に雲浜を訪ね、その紹介をもって中川宮に伺候し、十津川郷の由緒書を奉り、他日十津川が中川宮の恩遇を受ける端緒をつくった。文久3年(1863)3月再び中川宮に十津川郷の由緒を申し述べ、一郷挙げて王事に尽力せんことを奉願した。5月、ついにこの願いが聞き届けられ、十津川郷士は京都御所の警衛をすることとなった。維新5年前幕府の支配下を離れ“明治維新の魁”をなし得たことは、郷士達の年長者として、よくリーダーシップを発揮した藤左衛門の力に負う所が極めて大きい。
 天誅組の乱に当たっては8月18日の政変による、十津川郷の立場の変化を憂慮、収拾に当たり、上平主税と共に風屋福寿院にて伴林光平、乾十郎と会見、十津川退陣を決めて帰京する。滞京中藤左衛門は、中沼了三・坂本龍馬・中岡慎太郎・桂小五郎・大村益次郎・伊東俊輔・西郷吉之助等と会合、しばしば国事を論議した。明治になって十津川は神仏分離令により廃仏毀釈を断行したが、この挙は神を敬い、仏法を排した藤左衛門の果断によるという。明治2年(1869)郷内二流に分かれ相争う事態が生じ藤左衛門は反対党の為、激しく詰問され、又事態収拾の為、鎮撫使入郷を聞き、“郷士多年の忠勤一朝にして水泡に帰すのみならず、いまや天朝より厳責を被らん”と憤激、ついに病重り程なくして4月29日、込之上にて没する。享年64歳。従五位が贈られた。 天誅組の乱に当たっては8月18日の政変による、十津川郷の立場の変化を憂慮、収拾に当たり、上平主税と共に風屋福寿院にて伴林光平、乾十郎と会見、十津川退陣を決めて帰京する。滞京中藤左衛門は、中沼了三・坂本龍馬・中岡慎太郎・桂小五郎・大村益次郎・伊東俊輔・西郷吉之助等と会合、しばしば国事を論議した。明治になって十津川は神仏分離令により廃仏毀釈を断行したが、この挙は神を敬い、仏法を排した藤左衛門の果断によるという。明治2年(1869)郷内二流に分かれ相争う事態が生じ藤左衛門は反対党の為、激しく詰問され、又事態収拾の為、鎮撫使入郷を聞き、“郷士多年の忠勤一朝にして水泡に帰すのみならず、いまや天朝より厳責を被らん”と憤激、ついに病重り程なくして4月29日、込之上にて没する。享年64歳。従五位が贈られた。
生家の丸田家は豊中の日本民家集落博物館に移築され、大阪府指定有形文化財として保存されている。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|

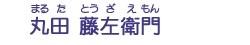
 天誅組の乱に当たっては8月18日の政変による、十津川郷の立場の変化を憂慮、収拾に当たり、上平主税と共に風屋福寿院にて伴林光平、乾十郎と会見、十津川退陣を決めて帰京する。滞京中藤左衛門は、中沼了三・坂本龍馬・中岡慎太郎・桂小五郎・大村益次郎・伊東俊輔・西郷吉之助等と会合、しばしば国事を論議した。明治になって十津川は神仏分離令により廃仏毀釈を断行したが、この挙は神を敬い、仏法を排した藤左衛門の果断によるという。明治2年(1869)郷内二流に分かれ相争う事態が生じ藤左衛門は反対党の為、激しく詰問され、又事態収拾の為、鎮撫使入郷を聞き、“郷士多年の忠勤一朝にして水泡に帰すのみならず、いまや天朝より厳責を被らん”と憤激、ついに病重り程なくして4月29日、込之上にて没する。享年64歳。従五位が贈られた。
天誅組の乱に当たっては8月18日の政変による、十津川郷の立場の変化を憂慮、収拾に当たり、上平主税と共に風屋福寿院にて伴林光平、乾十郎と会見、十津川退陣を決めて帰京する。滞京中藤左衛門は、中沼了三・坂本龍馬・中岡慎太郎・桂小五郎・大村益次郎・伊東俊輔・西郷吉之助等と会合、しばしば国事を論議した。明治になって十津川は神仏分離令により廃仏毀釈を断行したが、この挙は神を敬い、仏法を排した藤左衛門の果断によるという。明治2年(1869)郷内二流に分かれ相争う事態が生じ藤左衛門は反対党の為、激しく詰問され、又事態収拾の為、鎮撫使入郷を聞き、“郷士多年の忠勤一朝にして水泡に帰すのみならず、いまや天朝より厳責を被らん”と憤激、ついに病重り程なくして4月29日、込之上にて没する。享年64歳。従五位が贈られた。

