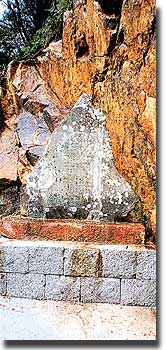|
|
|
|
|
 天保8年(1837)9月6日、父銀之助の長男として折立に生まれる。 天保8年(1837)9月6日、父銀之助の長男として折立に生まれる。
文武に秀で謹直にして、思慮深い人物であった。
幼年のころより、学問を好み、亀山藩士長沢俊平等に和漢の学を、田辺藩士安藤彦九郎等を招いて武技を学ぶ。幕末、文久3年(1863)十津川郷士は、京都御所警衛の任に維新までの約5年間従事した。この間滞京中の郷士達にとっての大きな問題の1つは、経費の捻出であった。高良は私財2,000余両を投じて、公費を補い、郷士の勤皇運動に大いに尽力した。
 |
| ●遭難地碑(宇宮原) |
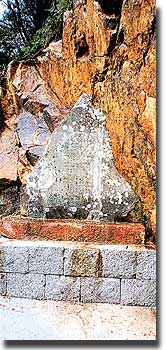 |
| ●玉置高良碑 |
天誅組の乱には、政変による混乱を同志と共に収拾に努めた。元治元年(1864)5月、松雲寺を仮校舎として郷校文武館が開館された。高良は校舎新築に努力し、11月平山に落成をみた。建築後文武館詰助役となり経営にあたった。次いで郷総代となり郷務の整理に当たる。明治5年(1872)玉置神社祠官となり、後、市町村制の改革による各役職に就く。13年(1880)4月、宇智吉野郡長に任ぜられ、至誠を以て郡民に接し、産業・教育の振興、道路の開削等に力を尽くした。22年(1889)8月17日、田戸街道(上葛川~田戸間)の開通式に臨み、帰途宇宮原の旅館に宿泊したが、折から紀和地方を襲った大暴風雨、いわゆる十津川大水害の為、19日夜山岳崩壊し、家屋と共に十津川に押し流された。時に年52歳であった。特旨をもって従七位に叙せられた。因に田戸街道12粁余の工事費の内、千数百円は高良の寄付によるものであった。住民はその徳を表す為、表徳碑を建立した(現在神下にある)。遭難地の宇宮原には「字智吉野郡長玉置高良君遭難碑」が有志によって建てられている。尚、洞川・吉野両地区は大峰山寺の領有権をめぐって、明治初期以来約10年間、相争っていたが、高良は郡長就任後、調停役を務め、非常な努力の末、解決に導いた。住民はその恩に感じ、洞川竜泉寺に表徳碑を建て、碑文中に郡長の恩“百世忘る可からず”と刻んだ。時を経て高良没後100年目、平成元年(1989)洞川区民はこのことを忘れず、高良の曾孫、当時の十津川村長玉置春雄を招き、天川村長を始め約100人、竜泉寺碑前において盛大な追悼、報恩法要を行った。11月10日のことである。
尚明治41年(1908)、吉野山に高良の高徳に報いる為、碑が建てられ、没後20年の大祭典が行われた。主唱者は東中の福井清重であり、経費は宇智吉野郡内有志家の醵金[きょきん]によった。 |
|
|
|
|
|
|


 天保8年(1837)9月6日、父銀之助の長男として折立に生まれる。
天保8年(1837)9月6日、父銀之助の長男として折立に生まれる。