
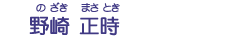
若くして、医学を亡父野崎秀易に学んだ。 秀易は三枝玄良の門人で、玄良の師は一橋家(御三卿の1、田安家・清水家・一橋家)の御典医(江戸時代、将軍家や大名に仕えた医者)である小野玄甫であった。 正時は明治16年(1883)内務省の医術開業免状を取得、川津の実家において村人の治療診察に当たった。正時は心広く、人情厚く、人を愛し、患者の病いを看ること、あたかも自分の病いを看るように真剣そのものであった。煩わしさをいとわず、営利を求めず、唯々ひたすらに村人の医療一筋に明け暮れた。 正時は医術に優れ、治療に熱心であったばかりでなく、村の雑事についてもよく世話をやき、時に応じて村人に人倫道徳を説いたという。為に村人は彼の人格高く、徳の高さに打たれ、賞を贈って感謝の意を表す事数度に及んだという。 医療に生涯をささげ、この地を終焉の地としたが、村人皆この人の亡き後、人情薄く風俗の乱れた末世の感のある今日、これを批正する正時のような人物が居なくなったら、道徳ということは無くなってしまうのでないかと、惜しみ憂い嘆き悲しんだという。 正時の没後、川津青年団が発起して村人の手によって、正時の徳を広く顕彰し永く伝えんとして頌徳碑が建てられた。 このことは正に故人を仰ぎ慕う村人の善行であり美挙というべきことであろう。 大正13年(1924)5月の事である。 碑文は浦武助十津川中学文武館教諭(後の館長)である。 この碑は昭和35年(1960)10月、風屋ダム築造のため、水没を避けて現在地の旧川津ユースホステルの庭に移された。 隣接して川津の生んだ天誅組の志士野崎主計の碑、明治維新勤皇の志士梅田雲浜顕彰碑が建っている。 |
|||||
 |
 |
