
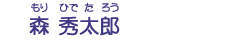
 慶応2年(1866)1月28日、父森平蔵母カンの長男として、内野に生まれる。 慶応2年(1866)1月28日、父森平蔵母カンの長男として、内野に生まれる。生来記憶力に優れ、生まれながら伝承者としての資質を備えていた。秀太郎23歳の時即ち、明治22年(1889)8月古今未曽有の大水害起こり、幸い生家は崩壊を免れたが田畑は流失し、十津川での生活の基盤を無くし止む無く、郷民600戸・2,600人と共に北海道新十津川村へ移住した。 移住後幾多の辛酸をなめ、後半生天理教団北海道教務支庁の常任書記を勤めたが、故あって職を追われ、失意と憂悶の余生を送り、その間欠かさず、微醺[びくん]低唱したのは「韓信が股を潜るも時世と時節…牡丹も菰[こも]着て春を待つ」の鴨緑江節であったという。北海道沼田村において、昭和17年(1942)9月、76歳の生涯を終えた。没後、上下2冊の懐旧録と数冊の日誌が残された。遺文原本は現在新十津川町の開拓記念館に保存されている。 昭和59年(1984)この資料を元に秀太郎の末子森巌(新十津川生まれ、札幌一中北大鉱山工学科卒、北見工大・北海道工大教授歴任、工学博士、北方生活科学研究所長)が編集、『懐旧録 十津川移民』として出版された。 移住前の十津川の生活状況、水害時の有り様、移住後の開拓の様子など克明に記録されており、「明治の常民による驚異の生活記録、第一級の民俗資料」と高く評価された。川津から神納川沿いの県道川津高野線、大字内野の道路端に「発跡地記念碑」が建つ。碑文には水害により森秀太郎が新十津川に移住した顛末が記されている。 水害の状況を伝える一部の記録を転記すると、 「上野地村では、川下から人家が濁流に乗り逆流して来るので、まさか山崩れのためとは知らず“これは海から支[つかえて]来るのじゃろう。昔話の泥海になるのじゃろう”と驚いて話し合っているうち、たちまち役場を呑んだ水は、上の段まで上がって来たので、慌てて山の上へ逃げた。宇宮原対岸の茶店は流失して、泊り客もみな溺死したが、ただ1人老人客が一瞬早く逃げ出し助かった。宇智・吉野両郡の郡長玉置高良氏は折立村の平石の主人だが、ちようどこの時下葛川から瀞へ車道が開削されたので、その開通式に出席して郡役所へ戻る途中、ここに泊まっていて遭難した。(後年ここに碑が建った)とにかく上野地も宇宮原も、平坦の田畑はみな流失したので、価値にすれば八分通りは失われたわけである。」 ・逆流にやられて(懐旧録P136より) |
|||||||
|
|||||||
 |
 |

