
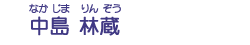
| 今から凡そ300年余り前、現在二津野ダムとなっている果無山の麓、桑畑に沿う十津川本流は、巨岩屹立、激流渦を巻いて、舟の運行は全く不可能であった。従って新宮から十津川郷への物資は総て、桑畑までは舟で、ここよりは人の肩により、果無山を越えるより方法がなかった。 当時この船着場に桑畑の住人で中島林蔵という人が商店を営んでいた。新宮から十津川へ、十津川から新宮へと総ての物資の集散地という地の利を得ていた上、商売熱心の為、店は繁盛し、そのあたりきっての財産家となった。 林蔵は生来、温厚にして人一倍情に厚い人情家であった。 日頃数里(1里:約4km)の山坂を越えて、生活物資を自分の店に求めなければならない難儀を思いやって、深く同情していた。 林蔵は、「あの大きな巌が無ければどんなに助かるだろうか」と思案に思案を重ね、遂に「たとえ自分の財産は無くなっても、村人の困難を救ってやろう」と固く決心した。 そこで数百金を投じて、石工を雇い自分も手伝って、多くの日数を掛けてとうとう大きな巌をことごとく打ち砕き、桑畑から上流小原まで、約5里の間舟の運航を可能にした。これが為、今まで人の肩によらなければ物資の運搬が何一つ出来なかった人々は、大変な恩恵を受け、非常な利益をあげ、地方の産業も大いに発展した。 ところが一方このことにより、林蔵の店は全く収益が上がらなくなってしまった。しかし、林蔵は一向に頓着せず、物資を山と積んで上り下りする舟を眺めて1人楽しんでいたという。 元禄15年(1702)赤穂義士討ち入りの年、正月5日、この世を去った。 犠牲的精神に満ち、身を捨てて人の為に尽くした生涯であった。 林蔵の生年は不詳である。 明治天皇御製 “おのが身はかえりみずして人のため 尽くすぞ人の誠なりけり” |
|||
 |
 |