
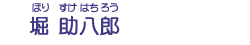
西の蔭地[おうじ]に住んでいたが、たまたま享保年間痘瘡の大流行があり、一家7人がこれに罹り、助八郎1人を残して全滅するという悲運にあった。このため、助八郎は亡くなった家族の霊を弔い、冥福を祈るため、自分の所有していた日浦山の全てを菩提寺の高岩寺(平谷にあった寺で、京都妙心寺中金牛院の末寺であり、山号を南谷山といった。現在奈良交通バス停横に切妻造りの四脚門、瓦ぶきの屋根の山門が残っている。)に寄付し、単身故郷を出、諸方を遍歴し遂に帰らなかった。 寄付された山は、寺領として受け継がれていたが、明治になって神仏分離令により、十津川は廃仏毀釈(寺を廃し神を祭る)を断行したため、高岩寺は廃寺となってしまった。 そのため、垣内・垣平・猿飼・山手の檀徒はこの山を等分し、夫れ夫れの所有地とし長くその恩恵をこうむることとなった。 昭和14年(1939)3月この恩に酬いるため、平谷学区民によって「堀助八郎氏記念碑」が建てられた。 碑は平谷福山神社下の高岩寺住職の墓地内にあり、碑文並びに書は平谷出身従四位医学博士中川小四郎である。 尚また、この助八郎の頌徳碑が県道龍神十津川線沿いの下湯、助八郎の寄付した山林領内の道路端にある。助八郎の徳を表す為、その由来を記し、昭和45年(1970)、山手・平谷・猿飼によって建立されたものである。 助八郎の生年、没年終焉の地何れも不詳である。 享保5年(1720)痘瘡の大流行があり、記録によれば死人が多く出たと記されているが、このことから類推すれば助八郎の生まれたのは元禄時代であったろうか。何れにせよ助八郎若年のころと察せられる時期、痘瘡の流行により父母兄弟を一時に7人も失うという、思いもかけぬ悲惨な事態に遭遇するとは、正に想像を絶するものがあり、彼が無常感の末全てを捨てて故郷を出た心情察するに余りあるものがある。 |
|||||||
 |
 |

