
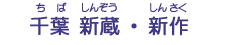
| 千葉新蔵は元文4年(1739)出谷字殿井に生まれた。 資性純良で朝夕孝養を尽くし、親の喜びをもって無上の楽しみとしていた。新蔵の母みつはかねてから、西国33カ所の巡礼を念願していたが、病と寄る年波の為、どうすることも出来なかった。母の心中を深く思いやった新蔵は、道中の心配もあったが、仏の慈悲を頼りに老母を背負って旅に出た。第1番の札所紀伊国那智山から、第2番紀三井寺までの間は遠く、母を背負った身には困難な道程であったが、親を思う新蔵にとってはものの数ではなかった。それから1年、和泉・河内・大和・山城・摂津・播磨・丹後・近江の霊場を経て、とうとう美濃の第33番札所にたどり着き、母の念願を叶えさせた。この新蔵の孝心が仏に通じたのか、母の病は全く癒えた。この時新蔵は仏の加護を深く感じ、報恩の為再び西国巡礼を行った。母みつはその後、新蔵の手厚い孝養を受け、天寿を全うした。 新蔵の長男新作は安永7年(1778)生まれで、親の性質を受け継ぎ、孝心厚く、田畑に出ては父の体を労り、身を粉にして働いた。
一・扇子一箱 五本入り 一・金百疋 一・六教解一冊 が下された。文化4年(1807)8月のことである。 翌年、老中松平定信の耳にも達し、新蔵に銀10枚が贈られた。 新蔵は文政3年(1820)81歳、新作は天保元年(1830)52歳で没した。 昭和11年(1936)父子の徳行を永く伝えるべく、村人達によって純孝碑が旧出谷小学校の校庭に建てられた。現在学校統合により西川第二小学校校庭に移転されている。碑文は出谷出身、文武館長浦武助である。 思うに親孝行といえば、日本的には二宮金次郎がその代名詞になっているが、我が村にも親孝行で、しかも父子共々親孝行な村人のいたことを知るべきであろう。 |
|||||
 |
 |
