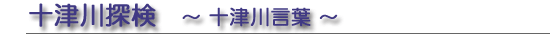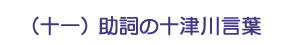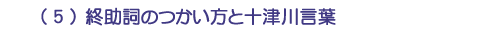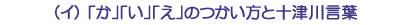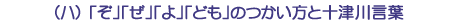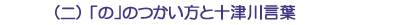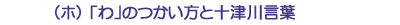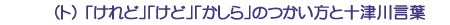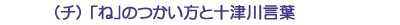|
|
|
|
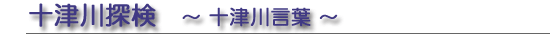 |
|
|
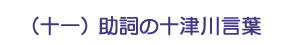 |
|
|
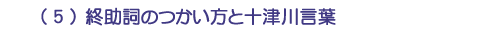 |
|
|
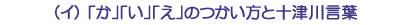 |
|
|
|
| |
これは何か |
疑問の「か」 |
|
そんなことがあるか |
反語の「か」 |
|
何を云っているんだい |
意味を強める |
|
勉強したかえ |
意味を強める |
「か」「い」「え」は上の如くつかわれ、十津川に於ても多く用いられる。
十津川では疑問の「か」や反語の「か」に「い」「え」「よ」をつける
| |
こりゃー何かい |
疑問 |
|
元気なかい |
疑問 |
|
こりゃー何かよ |
疑問 |
|
そがぁーなことんあったかよ |
疑問 |
|
こりゃー何かえ |
疑問 |
|
もう行たかえ |
疑問 |
|
ありゃー何ぢゃい |
疑問 |
|
そがぁーなことんあるかい |
反語 |
|
そがぁーなことー云う者があるかよ |
反語 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
心配するな |
禁止の意味を表す |
|
うれしいな |
感動咏嘆を表す |
|
今日は寒いなあ |
感動咏嘆を表す |
|
美しい花だなあ |
感動咏嘆を表す |
「な」「なあ」は上の如くつかわれるが、禁止の意味を表す「な」以外はあまりつかわれなかった。禁止の「な」にも「よ」をつけて「なよ」という。感動咏嘆の場合は「のう」と「のうら」を多くつかう。
また十津川では「がい」という言葉がある。これは「がなあ」と云う意味で矢張り感動咏嘆を表す言葉である。
| |
心配するなよ |
禁止 |
|
そがぁーな所え行くなよ |
禁止 |
|
うれしいのう |
感動咏嘆 |
|
いい天気ぢゃのう |
感動咏嘆 |
|
うれしいのうら |
感動咏嘆 |
|
いい天気ぢゃのうら |
感動咏嘆 |
|
この花は美しいがい |
感動咏嘆 |
|
大きな芋ぢゃーがい |
感動咏嘆 |
|
|
|
|
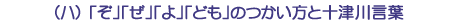 |
|
|
|
| |
さあ行くぞ |
強く指示する意を表す |
|
今度はうまくいくぜ |
軽く指示する意を表す |
|
全くすばらしいや |
感動強意を表す |
|
まあおもしろいよ |
感動強意を表す |
|
太郎やおいで |
呼びかけの意を表す |
|
太郎よ来なさい |
呼びかけの意を表す |
|
まだ走れるとも |
強意、確実な断定を表す |
上のようにつかわれ、十津川でも普通につかわれているが、「や」はあまり用いられない。殊に呼びかけの意を表す「や」は全然用いないといってもよい。 |
|
|
|
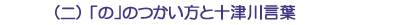 |
|
|
|
| |
どこへ行くの |
疑問を表す |
|
私がわるかったの |
軽い断定を表す |
「の」は上のようにつかわれるが、十津川ではあまりつかわない。然し疑問の意を表す場合に「のか」「ない」「ないよ」を多く用いる。
| |
どこえ行くのか |
疑問の意を表す |
|
私が悪かったのか |
疑問の形で軽い断定の意を表す |
|
どこえ行くない |
疑問の意を表す |
|
何が悲しいないよ |
疑問の意を表す |
|
|
|
|
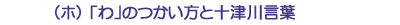 |
|
|
|
「わ」は上のようにつかわれる。
この「わ」という言葉は江戸時代に「わい」「わな」「わさ」と男女共通に用いられていた。それが明治初期になって「わ」となり、婦人のみが用いる婦人専用語となった。
然し十津川に於ては「わ」「わい」「わよ」など男女共通でつかわれている。
| 例 |
叔母ん来たわ |
|
ああ!よわったわよ |
|
おれも行くわい |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
これから行ってみないこと |
疑問の意を表す |
|
まあきれいなこと |
感動の意を表す |
|
仕事のじゃまをしてはいけないこと |
断定の意を表す |
|
だってくやしいんだもの |
理由、根拠を表す |
「こと」「もの」は上のようにつかわれるが、十津川に於ては「もの」と感動の意を表す場合の「こと」はつかわれるが、其の他の「こと」はおそらく用いない。 |
|
|
|
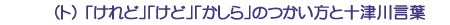 |
|
|
|
| |
もしもし…京子ですけど |
|
|
私もそう思うのですけれど |
余情を表す |
|
私によく似合うかしら |
自分自身、または他人に対して呼びかけながら疑問を表す |
「けど」「けれど」「かしら」は上のようにつかう。何れも婦人語である。
先に「かしら」について述べたが、先のは副助詞で副詞のような作用をする助詞であった。ここで述べるのは終助詞で作用がちがう。
然し「かしら」は「かしらん」の「ん」が脱落した言葉で十津川では終助詞の場合ももとのままの言葉で男女共通でつかわれている。
尚「けど」「けれど」は十津川に於ては「けんど」といって男女共通につかわれている。
| 例 |
おれもそがぁーに思うんぢゃーけんど |
|
おれも知っとったんぢゃーけんど |
|
おれによう似合うかしらん |
|
おれも行てみようかしらん |
|
|
|
|
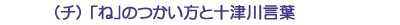 |
|
|
|
| |
これは美しいね |
感情余情を表す |
|
それはよかったね |
感情余情を表す |
上のようにつかうと終助詞になる。然し
| |
あのね、私がね、町えね、行ったらね、ほしい物がね、沢山ありました |
上のようにつかうと終助詞とせずに間投助詞という人もある。また
上のように言葉の一番先に「ね」をつけると、これは感動詞で既に述べた通りで助詞ではない。
十津川では「ね」はあまりつかわないで、多く「のーら」を用こる。
上のようにつかえば終助詞になり、
| |
あののーら、おれんのーら、町いのーら、いたらのーら、ほしいものんのーら、ぎようさんあった |
とつかえば間投助詞となる。また、
上のようにつかえば、感動詞で助詞でなくなるのである。 |
|
|
|
 |
|
|
|
「さ」は上のようにつかわれるが、十津川に於ては禁止、命令の言葉につけて意味を強める場合に多く用いられる。その時に語尾をのばすくせがある。
| 例 |
行けさー |
|
来るなさー |
|
見るなさー |
|
早う本を読めさー |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
そんなことがあるかいだ |
|
|
そこに居るがいだ |
強意を表す |
|
あいだ、ありゃーだ |
|
|
戻って来たがいだ |
強意を表すのであるが間投助詞のようにはたらく |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
みんな行けら |
|
正月に遊びい来いら |
|
さあ起きーら |
|
仕事ーせーら |
|
いたづらーするなら |
上のように「ら」は十津川に於ては動詞、助動詞の命令形(十津川では五段活用動詞以外の命令形はよ、ろ、を省いて語尾をのばすことは既に述べた)及び禁止の意味を表す終助詞について複数の命令の意味を表すと共に意味を強める。
| |
さあ起きろうら |
|
仕事をしょうら |
|
仕事をさしょうら |
|
絵をかこうら |
上のように「ら」は助動詞の「う」「よう」について「何々しようよ」という誘いかけの意味を表し、且つ意味を強める作用をする。
| |
さあ起きゅうらよ |
|
仕事をしょうらよ |
|
仕事をさしょうらい |
|
絵をかこうらい |
上のように「よ」や「い」を添えて余情を表す人もある。
| |
みんな行かぁーら |
|
人のことは見ぃーら |
|
まだ起きーら |
|
勉強させーら |
|
旅行に行かまいら |
上のように「ら」を動詞、使役の助動詞の「させ」及び推量の助動詞の「まい」等の未然形につけて「何々しないようにしようよ」と誘いかけの意味を表し、且つその意味を強める作用をする。
| |
こんな着物は着らーら(よ) |
|
あんな映画は見らーら(よ) |
|
まだまだ起きらーら(よ) |
|
もう考えらーら(よ) |
|
もうボールけらーら(よ) |
上の如く上一段動詞や下一段動詞の未然形に「ら」をつけて、その語をのばした上に再び「ら」をつけて「何々しないようにしようよ」と誘いかけの意味を表し、且つその意味を強める作用をする。
| |
太郎が走っつら |
太郎が走ったわ |
|
美しかっつら |
美しかったわ |
|
わやヂゃっつら |
めちゃくちゃだった |
|
先生が来るらしかっつら |
先生がお出でになるらしかった |
上のように「ら」を過去完了助動詞「た」の変化した「つ」につけて「つら」とし、これを、動詞、形容詞、形容動詞、助動詞の連用形に連続させて意味を強める作用をさせる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|