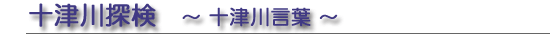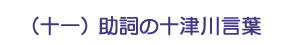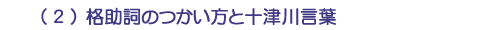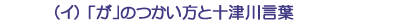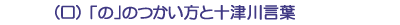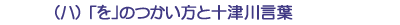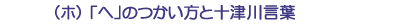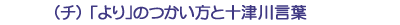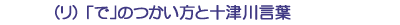|
|
|
|
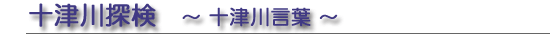 |
|
|
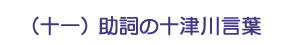 |
|
|
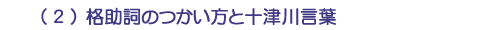 |
|
|
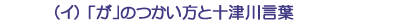 |
|
|
|
鳥が鳴く
水がのみたい
上の「が」は「鳥」、「水」という名詞についてその名詞が主語であることを示している。そして「鳴く」「のみたい」が述語で、主語と述語の関係にあることを「が」が示している。
十津川ではこの格助詞の「が」はあまりつかわず「ん」をつかう。
然し同じ格助詞の「が」でも「水がのみたい」の「が」は「水をのみたい」と「を」におきかえられる。この「を」におきかえられる「が」は「ん」にはならない。この場合は「みずーのみたあ」と主語の語尾をのばすくせがある。 |
|
|
|
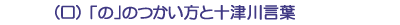 |
|
|
|
| (a) |
それはおれの読んだ本です |
| (b) |
しっかり持っているのだぞ |
| (c) |
彼は音楽の好きな人です |
| (d) |
そのきれいなのを下さい |
| (e) |
鉛筆だの筆だのいろいろ買った |
| (f) |
小鳥の声がきこえる |
格助詞の「の」には上の六種のつかい方がある。(a)と(c)の「の」は前に述べた「が」と同じく「おれ」「音楽」が主語であることを示している。
(b)の「の」は指示強調する意味を表す語である。
(d)の「の」は「されいな花」とか「きれいな絵」とかいう時の「花」「絵」のかわりに「の」を以って示しているので体言と同じ資格の語である。
(e)の「の」は事物の並列を表し、(f)の「の」は「小鳥」が「声」という語を修飾している連体修飾語であることを示している。
十津川に於ては(a)と(b)の「の」は「ん」になる。
| 例 |
そりやーおれん読うだ本ぢゃー |
|
しっかり持っているんぢゃーぞ |
(c)の「の」は「水がのみたい」の「が」に相当するはたらきをもっているので
おんがくーすきな人ぢゃー
と語尾をのばすのである。
(d)、(e)、(f)の「の」はそのままに正しくつかわれている。 |
|
|
|
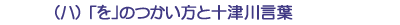 |
|
|
|
| |
手紙を書く |
動作の対象を示す「を」 |
|
橋を渡る |
経過する場所を示す「を」 |
|
故郷を去る |
動作の出発点を示す「を」 |
|
半年を遊んだ |
経過する時間を示す「を」 |
上の「を」はそれぞれ意味をもっているが何れもそのついている語が下の用言を修飾していることを示している。
然し十津川に於てはこの「を」を省略する。そのかわり「を」のついている語の語尾をのばす。
| 例 |
あ段 |
語尾が「あー」となる |
|
|
|
歯をみがく |
はぁーみがく |
|
|
山を登る |
やまぁー登る |
|
い段 |
語尾が「ゆー」となる |
|
|
|
木を切る |
きゅーきる |
|
|
火を炊く |
ひゅー炊く |
|
う段 |
語尾が「うー」となる |
|
|
|
徳をつむ |
とくぅーつむ |
|
|
犬を追う |
いぬぅー追う |
|
え段 |
語尾が「よー」となる |
|
|
|
手を入れる |
ちょー入れる |
|
|
家を建てる |
いょー建てる |
|
お段 |
語尾が「おー」となる |
|
|
|
戸をあける |
とぉーあける |
|
|
ろをこぐ |
ろぉーこぐ |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| (a) |
公民館に集まる |
場所を示す「に」 |
| (b) |
五時に起きる |
時刻を示す「に」 |
| (c) |
奈良に行く |
動作の帰着点を示す「に」 |
| (d) |
虫が蝶になる |
作用や変化の結果を示す「に」 |
| (e) |
呼びにやる |
動作の目的を示す「に」 |
| (f) |
人に物を貸す |
動作の相手を示す「に」 |
| (g) |
雨に降られる |
受身の場合にその作用の原因を示す「に」 |
| (h) |
風に家が倒れる |
動作作用の原因理由を示す「に」 |
| (i) |
甲は乙に等しい |
対比比較の目標を示す「に」 |
| (j) |
本に鞄にと整えた |
事物の並列添加を示す「に」 |
| (k) |
殿下にはお元気であらせられる |
尊敬する主語を示す「に」 |
| (l) |
しきりに、実に、互いに、さらに、 |
副詞をつくる「に」 |
上の如く「に」はいろいろな言葉を表すことにつかわれている。
十津川に於ては大体標準語の通りにつかわれているが(c)と(e)の場合は「に」を用いず「い」をつかう。これは ni の n が脱落して i だけが発音されるのであろう。
| 例(ⅰ) |
動作の帰着点を示す場合 |
|
|
奈良に行く |
奈良い行く |
|
平谷に行く |
平谷い行く |
|
こっちに来い |
こっちいこい |
|
あっちに行け |
あっちい行け |
| 例(ⅱ) |
動作の目的を示す場合 |
|
|
人を呼びにやる |
人を呼びいやる |
|
人を助けに行く |
人を助けい行く |
|
働きに出る |
はたらきい出る |
|
|
|
|
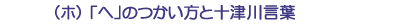 |
|
|
|
| |
南へ進む |
動作の方向を示す「へ」 |
|
頂上へ登った |
動作の帰着点を示す「へ」 |
「へ」は上のようにつかわれ、十津川に於ても普通につかわれている。 |
|
|
|
 |
|
|
|
| |
母と出かける |
ともにの意を示す「と」 |
|
秋も半となる |
作用や変化の結果を示す「と」 |
|
甲は乙と同じ |
対比比較の目標を示す「と」 |
|
友達と逢った |
動作の対象を示す「と」 |
|
手足と頼む |
比喩を表す「と」 |
|
筆と紙とを買う |
事物の並列の意を示す「と」 |
|
弟が旅行したいという |
引用を示す「と」 |
|
じっと、ずっと、そっと |
副詞をつくる「と」 |
上の如く「と」はいろいろな意味を表すことにつかわれる。十津川に於ても「と」は標準語通りにつかわれている。 |
|
|
|
 |
|
|
|
| |
旅から帰った |
動作の起点を示す「から」 |
|
前から三番目 |
順位の基準を示す「から」 |
|
御飯は帰ってからにします |
体言の資格を作る「から」 |
「から」は上の如くつかわれ十津川に於ても正しくつかわれている。 |
|
|
|
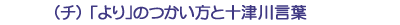 |
|
|
|
| |
歩くより楽だ |
比較の基準を示す「より」 |
|
それより仕方がありません |
限定の意を示す「より」 |
「より」は上の如くつかわれ、十津川でも普通につかわれるが、中には「よりか」と「か」をつける人が多い。
|
|
|
|
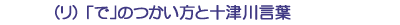 |
|
|
|
| |
庭で遊ぶ |
動作の行われる場所を示す「で」 |
|
後でします |
動作の起る時限を示す「で」 |
|
月賦で買う |
動作の行われる手段材料を示す「で」 |
|
病気で休む |
動作の行われる原因理由を示す「で」 |
「で」は上の如くつかわれ、十津川に於ても正しくつかわれている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|