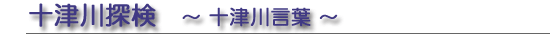
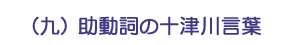
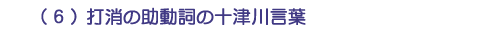
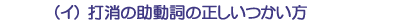
| 雨が降らない 試験が受けられない 上の「ない」は打消の助動詞で動詞や助動詞の未然形について打消の意味を表し、次のように活用される。 |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 上の外に打消の助動詞には「ず」「ぬ」「ね」「ん」がある。 危険な所に行かぬようにしなさい 何もいわずにいる方がよい 身のふり方をきめねばなりません |
||
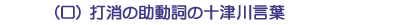
| 十津川に於ては「ない」と云う語より「ん」の方が多くつかわれる。 連用形の「なかった」は「なんだ」とつかう
仮定形の「なければ」は十津川では「にゃー」とつかっている。 行かにゃーならん 来にゃーならん 今、「行く」と云う言葉を十津川方言でどんなにつかうか書いてみよう |
||||||||
|
||||||||||||||||
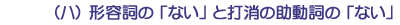
| この時計は新しくない この時計はくるわない 上の言葉を十津川言葉に直すと この時計は新しゅうなあー この時計はくるわん 同じ打消の意味を表す言葉であるが、一方は「なあー」となり、一方は「ん」となる。これはつまり同じように見えて性質が異なるからである。前の「ない」は形容詞で、後の「ない」は助動詞である。形容詞の方には「新しくもない」と「も」を入れることができるが助動詞の方には「くるわもない」と「も」を入れることができない。 十津川に於ては形容詞のないは「なあー」とつかい、助動詞の「ない」は「ん」とつかう。 |
||
 |