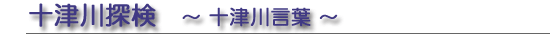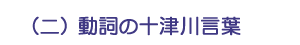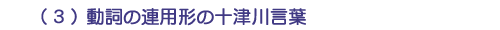|
|
|
|
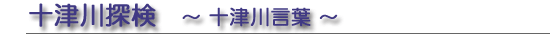 |
|
|
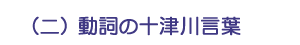 |
|
|
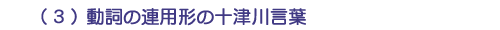 |
|
|
|
動詞の連用形が「た」「だ」に連続する時五段活用動詞の場合、十津川では語尾を変化させる。 |
|
|
|
 |
|
|
|
五段活用動詞でカ行に活用する語が「た」に連続する時、音便で「き」が「い」となって連なるのが正しい。
例えば「輝やく」という語が「た」に連なる時、「輝いた」となるのである。然し十津川では「い」を発音せず「かがやぁーた」という、ローマ字で示すと kagayaita が kagayata となり i が脱落して a がのばされる。
| 例 |
巻いた |
まぁーた |
|
咲いた |
さぁーた |
|
乾いた |
かわぁーた |
|
掃いた |
はぁーた |
|
焼いた |
やぁーた |
|
|
|
|
 |
|
|
|
五段活用動詞の連用形が「た」に連らなる時サ行に活用する語は語尾が変化することなくそのまま連続するのが正しい。
例えば「出す」という動詞は「出した」となる。然し以前は音便で「し」が「い」に変化して「出いた」と云った。こんな語は十津川でもカ行に活用する場合と同じく「だぁーた」という。
| 例 |
明した(明いた) |
あかぁーた |
|
挿した(さいた) |
さぁーた |
|
逃がした(逃いた) |
にがぁーた |
同じサ行の動詞でも「貸した」という語は音便で「貸いた」とはならない。こんな言葉は「かぁーた」とはいわない。 |
|
|
|
 |
|
|
|
五段活用の動詞の連用形が「だ」に連続する時、バ行、マ行に活用するものは音便で語尾が「ん」となって連なるのが正しい。
然し十津川では「ん」を発音しない、例えば「読んだ」という時、「よぉーだ」、とつかう。ローマ字で書いてみると
yoda となり yanda の n が脱落する。
| 例 |
ひそんだ |
ひそぉーだ |
|
呼んだ |
よぉーだ |
|
ころんだ |
ころぉーだ |
|
淀んだ |
よどぉーだ |
|
頼んだ |
たのぉーだ |
|
結んだ |
むすーだ |
|
休んだ |
やすーだ |
|
沈んだ |
しずーだ |
|
進んだ |
すすーだ |
|
ゆるんだ |
ゆるーだ |
上は語尾が変化しただけであるが、「噛んだ」という語は「こぉーだ」となり、語幹までが変化する。ローマ字で書いてみると kanda が koda となり an が o に変化して、その o がのばされる。
| 例 |
病んだ |
よぉーだ |
|
止んだ |
よぉーだ |
|
這んだ |
ほぉーだ |
|
いがんだ |
いごぉーだ |
|
かがんだ |
かごぉーだ |
|
|
|
|
 |
|
|
|
五段活用動詞の連用形が「た」に連なる時、ワ行に活用する語は音便で、語尾が「つ」となって連なるのが正しい。例えば「買う」という語が「た」に連なる時、「買った」となる。
然し十津川では「つ」を用いずに「こぉーた」という。ローマ字で示すと katta
が kota となり、at が o となってのばされる。つまり語尾だけでなく語幹までが変化する。
| 例 |
払った |
はろぉーた |
|
貰った |
もろぉーた |
|
笑った |
わろぉーた |
|
似合った |
によぉーた |
|
使った |
つこぉーた |
|
舞った |
もぉーた |
|
荷った |
にのぉーた |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|