
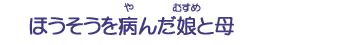

| 私の家の近くに、奥谷[おくだに]という谷があって、その谷の奥にタラタラという傾斜の緩[ゆる]い山原がある。 そこへ、私がまだ小学生の頃、母と薪[たきぎ]こりに行ったことがある。 私はゴシ、ゴシ、鋸[のこぎり]で木を伐って、ガリガリ、バシャンと倒した。木が倒れる時は愉快であった。母はそれを鉈[なた]でこなげた。 「次郎よ、はらんへっつろうがい。ひるめしゅう食おうら。」 という母の後について、私も山原へ下りた。弁当といっても、米が二分で麦が八分である。おかずは、梅干しとだしじゃこであったが、おなかがすいているとおいしかった。昼飯のとき、弁当を食べながら母は、こんな昔話を聞かせてくれた。 昔、このあたりゃあ樫尾崎[かしおざき]村ちゅうたんじゃ。この村にほうそう(天然痘)にかかった十五、六歳位の娘ん居ったんじゃと。ほうそうちゅう病気はうつり病いで、この病気にかかったら大方の人ん死んだんじゃ。ほんで、みんなおとろしがって、この娘の家へ、よりつかんようになったそうじゃ。 ほうそうにかかると、山の中へ小屋あ建てて、そこへうつされたんじゃ。この娘もここへ(タラタラ)小屋あ建てて入れられたんじゃと。 小屋ちゅうても、樫や椎の木のはしらあ突き立てて、屋根は杉皮でふいたんじゃ。壁は、はっぱのついとる木のえだあ横木にくくりつけたんじゃ。部屋のまん中へゆるりゅう(いろり)こしらえ、そのまわりに丸太あ並べ、丸太の上へ板あ敷き、板の上へ蒲[がま]むしろう敷いたもんじゃ。娘はそこへねさせられたんじゃと。 ほうそうが、うつったらかなわんちゅうて、誰も来る人んなかった。けんど、おか(母)は、 「こがあな山ん中へ、むすみょう(娘)一人ねかせられん。」ちゅうて、いっしょにきたんじゃと。 娘は、 「おりゃ、どうせ死ぬんじゃ。おかは帰れよ。おかまでほうそうになったらわるい。」 「ほうそうちゅうのは、うつってから何日もからだん中へ、すっこんどるんじゃ。おれももう、うつっとるじゃろう。おれのこたあ心配せんと早よう治せよ。」 おかは、そがあに言うてから、 「神様どうぞ、このむすみょう(娘)助けて下さい。」 と、祈りつづけておったんじゃと。そのうちにむすみゃあ治ってきたんじゃ。けんども、今度は、おかん熱う出しそめたんじゃと。ほうそうにかかってとうどうねこうで(寝込んで)しもうたんじゃと。 娘は起きて白粥うたあて(炊いて)おかに食わしたりして、おかあみたんじゃと。 「おりゃあ、としもよっとるし、とてもよう治らん。お前は、むりゅうしたらあかん。山あ下りて行けよ。」 「おかは、なにゅう言うない。治るわよ。じっと寝とれよ。」 娘は、一生けんめいにおかあ、みたんじゃと。 山の芋は栄養になるので、娘は、病[やみ]上りの青白い手で、山芋を掘り歩いたんじゃと。山の芋ちゅうのは、地べたに深こう、たてに入り込んどるので、なかなか掘れるもんじゃなあ、娘は、そりょう掘ってきて、おかに食わしたりした。 ほんでも、おかは、一日一日と病いが重うなって、とうどう死んでしもうたんじゃと。 山の動物ちゅうものは、人が死ぬと、よう知っとるのか、おおかめ(狼)ん、上の岡から「オー」、下の岡から「オー」とうなって小屋のまわりに、寄ってきて、柴壁[しばかべ]の間へ口を差し出すんじゃと。 娘は泣きもうて、火箸を焼きあて、おおかめの鼻へひっつけて夜を明かあたんじゃと。 おかん死んでも誰もきてくれん。娘は、小屋のそばへ穴あ掘って、おかあ埋めて山をおりたんじゃと。 二、三日してから来てみたら、おおかめん掘りだあて持って行ってなかったらしいよ。 |
|||||
|
|||||
 |