
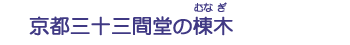

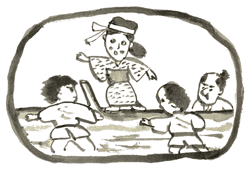 桑畑に柳本というところがある。そこには、古い柳の木があったが、道路が広げられたとき切られ、今では柳本という地名があったことさえ、知る人は少ない。 桑畑に柳本というところがある。そこには、古い柳の木があったが、道路が広げられたとき切られ、今では柳本という地名があったことさえ、知る人は少ない。むかしむかし、この山奥の柳本へ都から役人と大勢の人夫がやってきた。当時、この柳本には、天にも届くかと思われる柳の大木が一本立っていた。役人は、この柳の大木を切って都へ運ぶというのだ。 「都の天子様が大病にかかっているのじゃが、どんな祈祷[きとう]も薬も一向に効き目がないのじゃ。ところが天子様の夢枕に、み仏が現れて『熊野川の上流に柳の大木がある。それを都に運び、寺の棟木とし、わたしを祀[まつ]るがよい。』と、告げたのじゃ。われわれ一行は、三月[みつき]もかかって柳の大木を探し求めて、やってきたのじゃ。 ようやくここまで来て、この大木を見つけたというわけじゃ。ウーン、実に見事な柳じゃ。さすが、お告げの柳の大木だけあるわい。さっそくあすから切り倒しにかかることにしよう。」 そのとき、柳の葉が風もないのにかすかに揺れたようだった。 この柳の大木の近くに、老夫婦と一人娘が住んでいた。娘の名をおりゅうと言った。 この家に、以前から一人の若者が時おり通ってきていた。実にりりしい若者で、老夫婦は、二人をいつか夫婦[めおと]にしようと考えていた。若者は口数の少ない人だったが、「川下の者です。」と、いったことがあった。だから萩か本宮の人だろうと話し合っていた。 若者は鮎やアメノウオ、茸[きのこ]など、季節の土産を欠かすことはなかった。 今夜はどうしたことであろうか。若者の、あのにこやかな笑顔はなく、青ざめ、ふさぎこんでいた。まだ初秋ではあったが、山の夜気[やき]は冷たい。若者は黙ってチロチロ燃える囲炉裏の火を見つめていた。そして、思い切ったように、 「実は、今日、お別れにやってきたのです。全く突然ですが、急に都へ行かねばならぬことになりました。長い間、本当にお世話になりました。」 と、言うと板戸を開けて外へ出た。あまりにもす早い行動で、三人は声をかけることもできなかった。あわてて後を追った三人は、柳の大木の付近で姿を見失ってしまった。三人は悲しみに沈んでしまった。特に娘おりゅうの悲しみは大きいものであった。晴れて夫婦になることを夢見ていたのに、急に都へ行くのだという。 それも一切の理由を明かさないままに、である。裏切られたようにくやしく、身を裂かれるようにつらかった。その夜、誰も眠ることができなかった。 翌日から柳の大木を切る準備が始まった。都から来た人夫たちは、スルスルと大木をよじ登り、手早く枝を落としていく。むらの人たちの中には、手伝う者もいたけれど、めずらしげに見物している者が多かった。二、三日すると近在[きんざい]のむらからも、うわさを聞きつけて見物に来た人がいたほどである。一日中、あきもせず、作業する都の人夫たちを遠巻きにして見ているのである。 「オーイ、柳が倒れるぞ。」 という声が、あれから臥[ふせ]っているおりゅうの枕元まで届いたとき、 「おりゅうさん、さようなら。」 という、耳にささやく声を聞いたように思った。 はっとして、おりゅうが戸口まで出て見ると、枝を切り落とされた無惨な姿の柳の大木が、悲鳴のような音をたてて、ゆっくりと、そして、地響たてて倒れた。あたり一面、もうもうと土煙が舞い上がった。 やがて、柳の大木は、残った小枝を切り払われた。そして、大勢の人たちの掛け声とともに十津川へずり落とされた。 柳の大木は、水辺で他の丸太と一緒に太い藤カズラで結び付けられ、筏[いかだ]に組まれた。そして、水面に重たげに浮いた。何人もの力で、ゆっくり早瀬[はやせ]に押されていったが、いかにも流れていきたくない様子に見えた。むらの人たちは、妙にもの悲しい気持ちに襲われた。 おりゅうもむら人の中にいた。早瀬にのっても重々しくゆったり流れていく柳の大木を見送っていると、わけもなく涙があふれてきた。柳の大木はワラビオの瀬を越えて、やがて見えなくなった。 人々は、大きなためいきをついて、思い思いに散り始めた。大木の切り跡はがらんと広くなって、おりゅう一人だけが、切り株の側に立っていた。おりゅうは、どうしてそうするのか、自分でもわからなかったが、柳の切り株をいとおしげにさすっていた。ふと、おりゅうは、 -あの方は、この柳の化身だったのではあるまいか- と思った。 それから三日ばかり経った頃のことである。老母が、あの柳の大木のうわさを聞いてきた。 「なんでも楊枝[ようじ]とかいうところで柳がとまって動かないらしいよ。大勢で引っぱっても、木のまわりを掘っても、全然動かなくなったらしいよ。」 と、いうものだった。 その夜、おりゅうは、誰かが自分を呼んでいる気配に目が覚めた。起きあがったおりゅうの枕辺[まくらべ]に、あのなつかしい若者が、寂しい目をして座っていた。 「おりゅうさん、わたしです。あつかましいお願いですが、わたしと一緒に都へ行ってくれませんか。わたしは楊枝の川であなたが来るのをじっと待っております。」 -ああ、やっぱりそうだったのか。- おりゅうの目から、涙がとめどもなく流れた。そして、こっくりうなずいた。声が出なかった。 「それでは……。」 と若者は、おりゅうの目の前から消えた。 翌朝、おりゅうは、とめる老父母の手を振り切って果無山[はてなしやま]の道を本宮へと、たどっていた。狼がいる暗い寂しい道である。けれども、おりゅうは、おじることなく山道を登っていった。まだ、誰も通っていない山道は、くもの巣がはっていて、木の枝を振りつつ登っていかねばならなかった。 頂上付近で日の出であった。そこから尾根づたいに一気に八木尾[やきお]へ下りた。山ん婆の出るという山中であったが、今は、そんなことを考えている暇はなかった。 そして本宮。ここまでは、両親と来たことがあった。 本宮からまた山へ入った。この山を越えれば、楊枝である。しかし、中腹の小さなむらで日はとっぷりと暮れてしまった。おりゅうは、この名も知らぬむらのお宮に泊めてもらった。 あくる朝、まだ夜のあけきらぬうちに、おりゅうは楊枝を目指した。昼を過ぎたころ、ようやく、楊枝の川原に着いた。 川原では、なんとかして柳の大木を動かそうと、大勢の人が大騒ぎしている最中であった。浅瀬では、大木にそって深い溝が掘られていたが、いくら押しても引いても動かないという。今日で七日目であった。 おりゅうには、見おぼえのある都の役人の顔があった。その役人の前におりゅうは進み出た。 「申し上げます。私がこの柳の大木を動かしてご覧に入れます。夢枕に、私が掛け声をかければ必ず動くとの、お告げがありました。どうか、わたしにお手伝いさせて下さいませ。」 今まで動かなかったものが、女の掛け声ひとつで動くとは役人には思われなかった。しかし、この女は、もしかしたら特別の力をもった者かもしれん。一刻も早く動かしたい一念の役人は、おりゅうの力を試してみようと思った。 おりゅうは、柳の大木に近寄って、そっとささやいた。 「わたしが参りました。都までご一緒致します。どうか、安心して動いて下さいませ。」 やがて、おりゅうは大木の上にのぼった。りりしく黒髪にはちまきをしめ、手には扇をもって、居並ぶ何百人かの人夫たちに、 「みなさん、私が声を掛けましたら、みなさんも一斉に声を出して、力一杯引っぱって下さい。そうすれば神仏の力を得て、必ず動き出します。」 すみきったおりゅうの声を聞いた人夫たちも、体の内から新しい力がわいてくるのが感じられた。 「それではみなさん、心を合せて…… ソーレッ、ヨーイショ、ソーレッヨーイショ」 人夫たちも一斉に声を合せた。 するとどうだろうか。六日間ビクともしなかった大木が、そろりそろりと動き出したのである。人夫たちもこれにますます力を得て、さらに力を入れた。大木は、やがて早瀬にかかる深い渕にゆったりと浮いた。人夫たちは、歓声をあげておりゅうの元に走り寄った。 こうして柳の大木は、おりゅうにともなわれて新宮へ、そして海をわたり、淀川をのぼって、京に着いた。都の人々は、この柳の大きさに、たいそう驚いたという。やがて三十三間堂の棟木にされたのである。 ところでおりゅうは都にとどまったのだろうか、それとも両親の待つ柳本へ帰ったのだろうか。 |
||||||||
その他 |
||||||||
 |