


 奥里(大字内原)から三キロほどのところにソウハン渕がある。この渕は、そそり立つ絶壁の下にあって、どんよりと深く水をたたえている。渕は畳が何十枚も敷けるほど広く、ちょうど壷のような形をしている。おまけにこの渕は、周りがつるつるで、いったんはまりこんでしまうと溺れ死んでしまうとおそれられ、近付く者は今もいない。 奥里(大字内原)から三キロほどのところにソウハン渕がある。この渕は、そそり立つ絶壁の下にあって、どんよりと深く水をたたえている。渕は畳が何十枚も敷けるほど広く、ちょうど壷のような形をしている。おまけにこの渕は、周りがつるつるで、いったんはまりこんでしまうと溺れ死んでしまうとおそれられ、近付く者は今もいない。ソウハンというのは坊さんの名前らしく、この人が過[あやま]って、この渕に落ち込んで亡くなったという。それ以来ソウハン渕とよばれるようになった。 昔々、この奥里にたいそう孝行な息子がいた。長い患[わずら]いの父親がいたが、貧しい暮らしでは、ろくに薬も手に入らなかった。何とかして、早く元気になってもらいたいものだと、息子は気をもんでいた。 そんなある日のこと、朝から雨降りだった。こんな日は、一日中家の中で縄をなったり、ぞうりを作ったりすることになる。息子は、土間でぞうり作りを始めた。一段高いところに囲炉裏[いろり]があって、その近くに父親を寝かせている。 息子がふと表を見ると雨が止んでいた。青葉若葉がキラキラ光っているのをぼんやりながめていた息子は、 「父よ、おれ、今から釣りに行ってくるわ。ちょっと待っとってくれえよ。」 「雨上りの川は、そらあアメノウオがよう釣れるが、足元があぶないぞ。すべらんように気いつけて行ってこいよ。オイ、ソウハン渕だけには絶対行ったらあかんぞ。お前にもしものことがあったら……気いつけて行って来いよ。」 息子は、やせた父親の顔が、明るい外からはっきり見えなかったが、泣いているのだろうと思った。なんとしてでも父親に滋養のあるものを食べさせたかった。元気になってもらい、一緒に山仕事や畑仕事がしたかった。 雨の降ったあとは少し水も増し、ささにごりになっている。ミミズをつけて、チョンとゆるい流れに入れると、サッと一匹かかった。それからあとなかなか釣れない。奥へ奥へと移っていった。そしていつの間にかソウハン渕の上に来てしまっていた。 目がくらむ思いがした。みずかさも増し、水音も高い。どろりとした渕の底から水が沸き出すように渦まいているのだ。自分が吸い込まれそうな気持ちに襲われながら、懐からアワモチをとりだしてかじり始めた。気を落ち着かせる為もあった。じっと水の落ち口をながめていると、時々流れてくる川虫をねらっているのだろう、木の葉にまで飛びつくアメノウオが見えた。 釣ったものかどうか迷っていた。まだ、五・六匹しか釣っておらず、もう少しほしかった。このソウハン渕のアメノウオは、釣ってはならんと言われている。しかし、どうせ同じ川のアメノウオだ……。どうしたもんじゃろう。アワモチを口に入れたまま考え込んでいた。 そのとき、軽く肩をたたくものがあった。驚いて振り返ると、そこに旅を続けているらしい、一人の坊さんが立っていた。 「いやあ、驚かせてすまんのう。そなたがあまりに考え込んでいなさるようすなんでのう。一体、何を考えていなさる。」 「お坊さまは旅をしておいでですか……。別にたいしたことを考えているわけではありません。この渕の、ほれ、今、とびあがったアメノウオを釣ろうかどうか迷っておるんです。」 「どうして迷うのじゃ。」 「迷信だと思っておるんですが、昔から、この渕のアメノウオを釣ってはならんと……。」 息子は、自分だけがもちを食べていることに気がついて、あわてて坊さんにも渡した。 「おお、これはかたじけない。これはなんというものじゃ。」 「アワモチです。あんまりうまいもんではありませんが……。今朝方[けさがた]焼いたもんで、ちょっと堅いかもしれません。」 「いや、いや、けっこうけっこう。めずらしいもんじゃ。」 そういって、食いにくそうに食べていた。坊さんの姿をよくよく眺めてみると、墨染[すみぞめ]の衣の裾は裂け、破れた貴賤帽[きせんぼう]を冠[かぶ]っている。全身、雨に濡れてしまっている。 「ひとつ、そなたに頼みがあるんじゃが……。のう、もう幾匹か釣ったのじゃろう。それだけで満足してもらえんか。無益な殺生はするもんじゃない。この渕にそんな話があるんなら釣らん方がええと思うが……。昔から、してはならんということには、きっと何かわけがあるもんじゃ。」 「ウン、それはわかるのですが……。あと一匹だけ、と思うとるんです。……家では長い煩[わずら]いのお父が待っとるんです。……」 「わしは、先を急ぐんで、これで……。ごちそうになりました。では、くれぐれも頼みましたぞ。」 坊さんは丘を回って見えなくなった。 「どうしたもんかなあ……。よし、いっペんだけ竿を入れてみよう。それだけで終わりにしよう。」 そう決心した。丁寧にエサをつけて落ち込みの中へそっと投げ入れた。入れたとたん、すぐに強い当りがあった。なかなか上がってこない。相当な大物らしい。姿も見せない。小半時[こはんとき](三十分)も頑張って、やっと水面にその姿が現れた。それは、今まで見たこともないほど大きなアメノウオであった。ゾクゾクするほどの嬉しさが、体中を走った。糸を切られないよう、 「あばれるなよ、あばれるなよ。」 と、魚に話しかけながら、ゆっくりひっぱりあげた。とてもぼうつり(びく)に入るようなものではなかった。樫の枝を折って、えらに通して、かついで帰った。喜びが足元からはいあがってくるようで、胸もわくわくした。 「お父、今帰った。ほれ見てくれ。こんなどえらいもんが釣れた。」 それがどこで釣れたものかは、父親に言わなかった。 「じきに焼いたるよって、ちょっと待っとってくれえよ。」 そう言って、まず小さいアメノウオのはらをし、串にさし囲炉裏のふちに並べた。 さて、大物である。しばらく、その姿に見とれていた。包丁を入れるのが惜しい気がした。ちょっと迷っていたが、白い腹に思い切って包丁を入れた。手をつっこんではらわたを取り出す。これだけの大物だとはらわたも大きい。中でも胃袋が大きくふくれている。息子は気になった。 「いったい何を食べているのだろう。」 そんな興味もあって胃袋を裂いてみた。川虫に混じって黄色いものがたくさんある。 「これはなんだ。」手についたものをしげしげと見つめていた息子は、アッと息を飲みこんだ。アワモチなのだ。あのソウハン渕で 「頼みましたぞ……」と、 言い残して、去っていった坊さんが食べたアワモチであった。 息子は包丁をにぎったまま、破れた貴賤帽と裂けた墨染の衣を着て、濡れて去っていった坊さんを思い出していた。 |
||||||||
|
||||||||
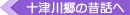 |