


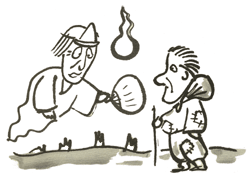 ある百姓家[ひゃくしょうや]のことである。母親は、長い間患っていたが、とうとうなくなってしまった。 ある百姓家[ひゃくしょうや]のことである。母親は、長い間患っていたが、とうとうなくなってしまった。残されたのは、父親の安蔵[やすぞう]と息子の安太郎[やすたろう]だけで、毎日、寂しく暮らしておった。しかし、悪いことは重なるもので安蔵までが病気になってしまった。やがて、この家の食べ物も底をついた。 あわれに思った庄屋は、二人を自分の家に連れてきてめんどうを見始めた。 庄屋の親切で、父親はずい分と良くなった。 ある日のこと、安蔵は、 「おかげ様で、もうすっかり良くなりました。たいへん気ままなお願いですが、私を旅に出して下さい。四国参りに行きたく思います。途中で死んでも構わぬ覚悟で参ります。息子の安太郎は、くれぐれもよろしくお願いします。」 真剣な安蔵の願いに心優しい庄屋は、胸を打たれてしまった。 本当に、この病み上がりの体では、途中でのたれ死にしてしまうかもしれない。しかし、安蔵の本望であれば仕方のないことだ、と庄屋は思った。 安蔵は遍路[へんろ]の姿となって、旅立って行った。 残された安太郎は、しばらく元気をなくしておったが、これではいかんと思ったのだろう。 「庄屋様、ずい分長い間お世話になりました。このまま毎日、ただ飯をいただいておりますと、申し訳ありません。何でもいたしますので、仕事をさせて下さい。」 と頼んだ。 庄屋も、 「なかなか感心な心掛けじゃ。働けば体にも良いじゃろう。 どうじゃろう、この屋敷の向こうに低い丘があろう。あの丘をいつまでかかっても良いから、この前にある畑と同じ高さになるまで掘り下げてくれんか。」 と言った。 早速、安太郎は仕事にかかった。毎日少しずつ丘を掘り下げていった。そんなある日のこと、ガチッと鍬[くわ]の先が一個の壷を掘り出した。ふたをとってみると中に大判が三枚入っていた。 すぐ、庄屋にそれを見せた。庄屋は、 「それはどれくらいの深さにあったか。三尺(一メートル)より上だったら地主のものだが、三尺より下だったらお前のものだよ。」 という。 「庄屋さま、三尺より上でした。どうぞ、お受け取り下さい。」 と言うと、 「いや、お前は、きっと嘘を言っておる。わしに、どうしても受け取らせようとしておるのじゃろう。それは、お前のものじゃ。」 と言って、どうしても受け取ってくれなかった。 困った息子は、代官所へ大判をもっていった。そして、代官に、 「庄屋様がどうしても受け取ってくれません。なんとかして下さい。」と訴えたのであった。代官は、庄屋の言い分も聞いたが、すっかり感じ入って、判断を下してくれなかった。今度は、お寺にもちこんで坊さんに訳を話し、 「寺の宝として受け取って下さい。」 と言うと、坊さんは、 「では、寺の宝として預っておこう。」 と、言うてくれた。 一方、四国へわたった父親は、二年間で四国中を巡礼し、ついに三年目、国元へ帰ることになった。四国を離れ、そして、とある村に入った。一夜の宿を求めたが、四国とちがって、どこへ行っても泊めてくれず、 「あっちの在所へ行け。」 「いや、向こうの在所へ行け。」 と、追い払われた。 仕方なく隣村へ行こうと三十町(約三キロ)ばかり登り切った休場[やすば](休憩所)まで来た。そこで大きな松の木にもたれて休んでいると、突然、もたれておる木の上から、 「おお来てくれたのか、待ちかねたぞ。」 と、叫ぶ者があった。すわっ、追いはぎと、びっくりしてはね起きた目の前へ、一人の男が音もなく降りてきた。 それは、六十歳ばかりの爺さんであった。 「あんたは、誰ない。」 と聞くと、 「いやあ、おどろかしてすまんすまん。実は、おれは幽霊なんじゃ。わしは、あんたが行く次の村に住んでいた者じゃが、何の罪もないのに、そこの大庄屋[だいしょうや]に殺されたんじゃ。恨みをはらそうと思うて、毎夜、大庄屋の門前まで行ってみるんじゃが、門にお札がはってあるんで、どうしても中に入れんのじゃ。一緒に来てくれ、あんたの来るのを、ずっと待っていたんじゃ。」 と言った。 そこで連れもうて、また三十町ばかり下りていくと、大きな屋敷の前に出た。幽霊は、 「そこのお札をはがしてくれ。」 と言った。 それをはがしてやると、 「おれが敵を討ってくるまで、ここで待っていてくれ。」 と、屋敷の中へ入って行った。 しばらく木の陰にかくれて待っておると、 「やれ、よかったよ、長年の恨みをはらしてこれたよ。実は明日、大庄屋が死んだという触れが出るから、二、三日おれの家に泊まっていってくれんか。」 と言う。 そして、一本の団扇[うちわ]をくれた。 「この団扇はな、孫がおれのガンバコ(棺)へ入れてくれた渋団扇[しぶうちわ]じゃ。これをもって行けば、孫はわかってくれるはずじゃ。あんたに団扇をやったのじゃから、わしにも何かくれんか。」 と言った。 そこで、安蔵はフダバサミのお札を一枚やると、 「ああ、ありがたい。ありがたい……。おお、そうじゃ。おれの家は、ここから二町ばかりのところにあるが、一軒屋じゃからすぐわかる。」 そういって、両手でお札をパリッと割いて、握ったかと思うと姿を消してしまった。 幽霊に言われたとおり、一軒の貧しげな家があった。門口に立つと、婆さんが孫を負うて出てきた。安蔵が遍路姿であったので、手の内(銭)をくれようとした。すると、背中の孫が安蔵のもっている団扇に気付いて騒いだ。そこで、婆さんに、これまであったことを話すと、婆さんは、たいへん喜んでくれたのであった。 翌日、幽霊の言ったとおり、大庄屋が死んだという触れが回って来た。安蔵は婆さんに二、三日やっかいになったのち、再び故郷へ向かって旅に出た。 一方、安太郎は、その正直さがお城にまで聞こえて、殿様に呼ばれることになった。殿様は安太郎の心根[こころね]にほれて、二百五十石の扶持[ふち](給料)をつけてくれた。 「武芸も学問もありませんから、どうか、お許し下さい。」 と断ると、 「人間は、正直が第一の宝じゃ。」 と、ますます気に入られて、若党や馬の口取り(けらい)までつけ、おまけに大きな家まで村の中に建ててくれた。 妻がないというので世話する人があって、ある侍の娘をもらった。やがて二人の間に男の子が生まれた。ところが、嫁さんは、安太郎にちっとも赤子の顔を見せなかった。安太郎は、侍というものは、自分の子どもも見られないのかと、変に納得して、そのままに幸せな時は過ぎていった。 さて、父親の安蔵であるが、ようやく故郷にたどり着いた。息子が世話になっている庄屋の屋敷に入る前に、もうこれで遍路としての修行はできないのだからと、村内[むらうち]を一回りしてこようと思った。 村の中に入ってびっくりした。自分が村を出るとき、こんな大きな家はなかったはずだ、と思いながら門前に立つと、美しい嫁さんが出てきて手の内を与えてくれた。そこを出てゆくと、向こうの方から立派な侍がクツワ取りと若党を連れて馬に乗ってやってきた。あわてて脇道によって近づいてくる侍をながめた。どうも見おぼえのある顔だが…はて…。 侍が近付いてきたので、思わず頭を下げた。侍は、安蔵のそばまで来ると、馬をとめてじっと見つめていたが、いきなり馬からとび下りると、じっと安蔵の顔をながめた。 「お父さんではありませんか。よく、まあご無事で…。」 あとはことばにもならず、むしゃぶりついてきた。安蔵は、夢かと一瞬思ったが、自分の胸に顔をうずめている侍は、確かにわが子安太郎であった。 安太郎は屋敷へ父親を案内した。その屋敷というのは、さっき、手の内を受け取ったところである。 嫁が出迎えに出て来た。けげんそうな顔をしている嫁さんに、安太郎は、 「お前に初めて会わすが、三年近く四国参りに行っておったわしの父上じゃ。」 と紹介した。 嫁さんは「エッ。」と驚きの顔付きとなり、そして、突然、泣いて泣いて、 「お父様とも知らずに手の内を出してしまって誠に申し訳ないことを致しました。本当に私はどうしたらよろしいのでございましょう。」 「いやいや、そんなことを気にせんでもよろしい。お互い親子ということがわからなんだんじゃからのう-。それよりも孫が生まれておるというが、見せてくれんか、早よう見せてくれんか。」 こう安蔵が言うと、嫁さんはまたまた泣き出した。 「一体どうしたのじゃ。」 と安蔵が問うと、 「申し訳ございません。実は不具[ふぐ]の子を産んでしまったのです。それで、まだ旦那様にも見せていないのです。こんな子を産んでしまって、本当に申し訳なく思っているのでございます。」 「なに、不具だと、不具でもよい。わしのかわいい初孫じゃ。さあ、早よう見せてくれ。」 「生まれて三十日もたつというのに、まだ目も開かず、手も握ったままなんです。」 と、涙ながらに言う。 「そうかそうか、とにかく会わせてくれ。初孫を見たいのじゃ。」 涙をうかべたまま嫁が離れ座敷に案内すると、赤ん坊はスヤスヤと眠っているふうだった。目は閉じ、両手もしっかり握ったままであった。安蔵は持っていた数珠を赤ん坊の目に当てた。そして、何やら文言を誦[とな]えると、目はパッチリ開いた。また、文言を誦えて数珠を両手に当てると、両手はゆっくり開いた。その開いた手の中に何やら紙きれのようなものがあった。安蔵がそれをつまんで開いてみると、なんと、それはあの幽霊に与えたお札であった。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
 |