
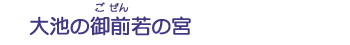

 今から二百年ほど前のことである。 今から二百年ほど前のことである。上野地の川向い、なかしまというところは、そのころ人家も多く、豊かな田畑が広がっていた。ところがいつの頃からか、何者かによって作物が荒され、収穫も少なくなった。 なかしまに「中根[なかね]」という金持ちがいた。この家にお若という美しい娘が、女中として働いていた。その立ち働く姿は、まるで野中の百合[ゆり]のようで、村の若い男たちのあこがれの的であった。 ところが、このごろどうしたことか、あれほどよく働いていたお若が、物思いに沈み、ため息まじりに、ぼんやり川面をながめていることが、目立つようになった。 こうしたお若のようすに気づいた中根の主人は、 「お前は、このごろどうしたんじゃ、何か悩んでいるように思うんだが、心配ごとがあるんなら、わしに打ち明けてくれんか、お前の力になることができると思うんじゃあが……。」 お若は、顔をうつむけたまま、何も話さなかった。そんなお若を見て主人は、少し声をあらげた。 「お若、お前は、わしが何も知らんと思っとるんじゃろう……。お前のところへ毎夜たずねてくる男は、一体、どこの誰なんじゃ。 わしは、お前を預っているんじゃから責任もある。教えてくれんか。丸くおさめてやろう。」 ところが、お若は黙ったままである。それもそのはず、お若は自分をたずねてくる男が、どこの誰だか、まったく知らなかったのである。 しかし、お若は、その男が、ただ者ではないことを初めから知っていた。男が訪ねてくるとき、戸を開け閉めすることはなく、スーッと煙のように現われるからである。 困りはてた主人は、 「どこの誰ともわからん男に、預かった大切なお前を会わすわけにはいかない。どこの誰なのか、お前も知りたいじゃろう」 お若は、こっくりうなずいた。 「よいか、男の気付かぬうちに麻糸をつけた針を、たぶさの中に差し込んでおくのじゃ。その糸を追っていけば、どこの誰かは、すぐにわかるじゃろう。お前もわしも安心というもんじゃ。」 さて、その夜のこと、お若は主人の言いつけどおり、縫い針に白の麻糸をつけ、男のすきをみつけて、たぶさの中にそっと差し込んだ。 夜が明けた。中根の主人は、起き抜けに、お若の部屋の裏に出た。 麻糸は朝露に濡れ、垣根越しに畑に降り、そして昼なお薄暗い薮の中を通り、やがて、なかしまのはずれにある、油を湛[たた]えたような大池の底深くへと沈んでいた。 アッと叫んだ主人は、腰も抜かさんばかりであった。こけつまろびつ、真青になって家にたどり着いた。 主人から糸の行方を聞かされたお若の驚きは、大変なものであった。お若が夜な夜な語り合ってきた相手がなんと、大池の主であったとは。悲嘆にくれたお若は、その日から部屋に閉じ込もり、一歩も外へ出ようとしなかった。食事もとらず、日に日にやせ細り、人々のあわれをさそった。 お若の顔付きは、日毎に何かにとりつかれたようになった。あの初々[ういうい]しいお若とは、似ても似つかなくなっていった。 ある嵐の夜のことである。ガタガタと戸を開ける音に気付いた家人が部屋にとびこむと、開けられた戸の向こうの薮へ走り込もうとするお若の姿が、キラッと光ったいなずまの中に一瞬見えた。そして、闇の中に吸いこまれていった。 その後、嵐の夜は決まって、青い火がただひとつ大池の周りをさまようのであった。 このことがあってから、なかしまの田畑が荒れることはなかった。 お若をあわれに思った村人は、大池のほとりに小さな祠[ほこら]を建て「大池の御前若の宮(お若大命神)」として、毎年、祭を行った。付近の村では、 「かわいい娘は、なかしまへやるな 上は立崖[たちくら]、したも崖[くら] 中に蛇[じゃ]の巣の池がある」 と、謡[うた]われた。 明治二十二年の大洪水で、なかしまは厚い土砂の下になってしまった。が、大池だけは、わずかにその跡を残していた。 毎年行われる国王[こくおう]神社の祭礼の日、行列が、なかしまの真向いの一本松付近に来ると、そこから大池の御前若の宮に向って、感謝の一礼をするのがならわしであった。 |
||||||
|
||||||
 |