


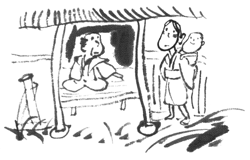 ずっと、昔の話である。松柱のある家の父さんは丸太切りで、山へ泊まり込んで仕事をしていた。 ずっと、昔の話である。松柱のある家の父さんは丸太切りで、山へ泊まり込んで仕事をしていた。ある夜のこと、誰かが戸をたたくので、開けて見ると、嫁さんが子供を背負って立っていた。びっくりしている父さんに、 「子供が、どうしても父さんの所へ行こうら言うすか(ので)、連れて来たんじゃ。」 と言った。父さんも一時は変に思ったが、子供の顔を見ると機嫌も直り、 「まあ、入れよ。」 と、小屋に入れた。嫁さんは、子供を背負って中に入って来ると、 「ああ、腹へった。」 と言うもんだから、飯の用意をして、たらふく食べさせた。しばらくして、 「今日はもう帰れ、あんまり遅うなってもいかん。」 と言うと、嫁さんは子供を背負うてさっさと帰って行った。 あくる夜になると、夕べと同じころ、嫁さんが子供を背負ってやってきて、 「子供が、どうしても父さんの所へ行こうら言うすか、連れて来たんじゃ。」 と言ったと。そして、腹がへったと言うもんだから、たらふく食べさせて帰らせた。次の夜、またまた同じころ、嫁さんは子供を背負ってやって来た。そして、「子供が、どうしても父さんの所へ行こうら言うすか、連れて来た。」 という。どうも、おかしい。 「いつもいつも、こんなに夜遅う飯を食らいに来て。もしも、明日の晩、お前らがここへ来たら、この鉄砲でうつぞ。」 と怒りながらも飯を食べさせて帰らせた。 それにしても不思議なことだ。こう度々来られてはたまらん。とにかく明日は家に帰るとしよう。 翌日家に帰り、これまでのことを嫁さんに話した。嫁さんは、そんなことはしていない、全く知らぬことだという。いくら確かめても知らないというのは本当のようだ。それならよい、嫁さんを疑う余地はなさそうであった。 それでは、昨夜まで来ていた者は何者であろう。いよいよ不思議でたまらない。不安がないわけでもないが、 「もし、お前らが、また、小屋へ来たら本当にこの鉄砲でうつからな。絶対に来るなよ。」 と、きびしい声で何度も念を押してから山へ出かけて行った。 仕事を終えて、夕飯もすまし、あれだけ言っておいたんだから、よもや今夜は来ることもなかろうと、休んでいると、意外にも、いつもと同じころ、嫁さんが子供を背負ってやって来た。 「子供が、どうしても父さんの所へ行こうら言うすか、連れて来た。」 と言った。こいつはただ者ではない。よくもずうずうしく来られたもんだ。油断していたら命が危ない、と思い、 「昨日あれだけ言ったことがわからんのか。今日来たら鉄砲で撃ついうたこと覚えとるじゃろ。」 と言うが早いか、そばにあった鉄砲を取って、逃げようとする嫁さん目がけて一発ぶっぱなした。 嫁さんは泣き泣き、 「これまで一緒に暮らして来て、こんな目に合わされるなんて…。」 と撃たれた傷を押さえ、泣き叫びながら逃げていった。 父さんも、一時は恐ろしさと腹立たしさとでかっとなり、嫁さんを撃ってしまったが、少し気が落ち着いてくると、やはり気になって、たいまつをつくり、後を追った。たいまつを明かして見ると、まだ、真新しい血が道にそって落ちている。しだいに心臓も高鳴ってくる。胸さわぎもする。足どりも早くなってくる。血のあとは、家まで続いている。家に着くとあわてて戸を開け、いきなり飛びこんだ。 部屋では親子は、いつものように寝ていたが、気の立っている父さんは母子をゆり起こし、 「今日、あれだけ言ったのに、お前ら、さっきおれの小屋へ来たな。」 と、大声でどなると、 「行きゃあせんぜ。」 と嫁さんがねぼけまなこで言った。それでも、まだ信じられない父さんは、 「うそつけ、確かにさっきお前ら、おれの小屋へ来とったんじゃ。」 「うそじゃない。行きゃあせん。-そういゃあ、さっき、牛小屋のあたりで、何かうなるような声がしよったわ。」 と言う。嫁さんも起きて来て、たいまつを持って一緒に牛小屋に行った。血は牛小屋のそばの大木へ続いている。よくよく見ると、腐ってあいた木の穴へ、飯をたくさんつめこんで、真白な大きなたぬきが、血まみれになって死んでいたということだ。 |
||||||||
|
||||||||
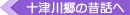 |