
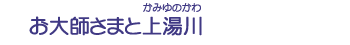

| 高野山は弘法大師さまが開いたことで名高い山じゃ。 その大師さまが、高野山を開くまでに、全国各地を修業して歩いたのじゃが、そのおり、この上湯川[かみゆのかわ]へも立ち寄られたらしいのじゃ。とくに、大師さまは、人びとが修業するのにふさわしい道場をどこに開くかと、各地を旅して探したようじゃ。 上湯川の上流、古谷[ふるや]川に今でも「見残し滝」というのがある。 これは、大師さまが、谷々を調べ数えるうちに、この滝だけ見落したらしく、それでその名がついたらしい。この見残し滝は、寺垣内[てらがいと]の少し上の、大野というところにあるのじゃ。 上湯川の古道[ふるみち]を歩いて行くと、道端に「大師がわらじを履き替えたところ」というのがあって、里の人びとは、そこを通るときには榊や花を供えたものじゃった。 また、梅垣内[うめがいと]の奥に、大師さまが旅の途中、お弁当を食べたとき使った箸を地面に差したら、のちにその箸が根を下ろし杉の大木になった、といい伝えられた大杉があるのじゃ。この大杉は、地上三メートルほどのところで三本に枝分かれした大木で、一二〇〇年の年令[とし]を数えるといわれる。里の人びとは三本杉と呼んで大切にしているのじゃ。 大師さまは、山の中でのどが渇き水に困った。 そこで、旅する者が、こんな山中で水がなくては、たいへんだろうと、この三本杉のところで水が湧き出るようにと祈り、きれいな水を導き出されたと言い伝えられている。この清水は、今も尽きることなく、こんこんと湧き出ているのじゃ。 |
||||||||
|
||||||||
 |