
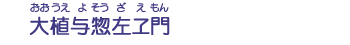

| 昔から十津川を経て高野へ通じるこの街道は、人里を離れたさびしい峠越えで、難所も多く、旅人は山賊などに悩まされることもたびたびあったという。 今から三百年余り昔のこと、慶長年間のころのことだそうだ。西中[にしなか]より坂道を登り、ひと汗かいた旅人は、みな、古矢倉[ふるやくら]の茶屋で疲れを休めるのである。そして三浦峠を越え、高野への旅を急ぐのであった。 ある時、この茶屋に山賊が立てこもり、旅人をねらって持ち物をうばい取るということがあった。旅人はもちろん、村人もこの山賊には、ほとほと困り果てていた。 そこで、各村の代表が集まっていろいろ相談した結果、この山賊を退治できるのは、与惣左ヱ門の他にはなかろうということになり、お願いすることになった。 大植与惣左ヱ門という人は、豊臣の家臣であったが、少々事情があって、十津川村の上湯川の上北[うえぎた](千葉家)の上の家に秘かに隠れ住んでいた。 人々の願いを聞いた与惣左ヱ門は、快く引き受け、さっそく山賊攻めの計画にとりかかった。綿密な計画を立てるため村の代表と話し合いをすすめていった。いよいよ計画の実行となり、手勢[てぜい]を集め、茶屋を攻め、みごとに山賊を打ちはらったということだ。 何しろ、与惣左ヱ門は、非常に知恵がある上に豪傑で、しかも、なかなかの弓の名人であったという。だから、さしもの山賊も与惣左ヱ門の知略には勝てなかったということだ。 その時、賊から奪った自在鉤[かぎ]と鑵子[かんす](つるのついた湯がま)は、上北(千葉家)に保管されているということだ。 話かわって、昔は出谷[でだに]・上湯川[かみゆのかわ]とも西川谷と一緒に玉垣内[たまがいと]の川合神社を祀っとった。ところが、川合神社のお祭りの餅投げの時になると、たびたびけんかが起こった。 慶長十年六月一日、川合神社のお祭りの時、餅投げが始まると、またまたけんかが起こった。 「これは困ったことじゃ。こうたびたびけんかが起こるようじゃ、何とかせねばならん。」 という人々の声が高まると、それぞれの村の人々の話し合いがもたれた。その結果、上湯川からは、大植与惣左ヱ門が、出谷からは千葉重左ヱ門が、それぞれ両村の代表となり、西川谷の代表と話し合い、騒ぎをしずめたということだ。 二人は、さらに西川谷の代表と話をすすめ、川合神社の神霊[しんれい](みたま)を分霊して、それをそれぞれの村に迎えて祀るということまでの了解も取り付けたそうだ。その話がまとまると、さっそく、与惣左ヱ門は杉の葉を、重左ヱ門はよもぎの葉をそれぞれもって神前に深く祈った。そうして、みたまを受けて帰り、祀り始めたのが上湯川の天神様であり、出谷の天一神社の起源だと今に伝えられている。 |
||||||||
|
||||||||
 |