


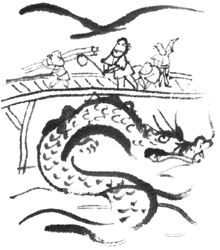 小井[こい]にある大矢の谷(親谷[おやんたき])には、いくつもの滝があって、深い渕には、水がドロッとよどんでいる。 小井[こい]にある大矢の谷(親谷[おやんたき])には、いくつもの滝があって、深い渕には、水がドロッとよどんでいる。今から二百年も昔のことである。夏のころ大雨が降り続いて大矢の谷に架けてあった丸木橋が流されてしまった。この橋は池穴[いけあな]と小井とを結んでいた。 村の衆らは、木のひきかけた頃を見はからって橋を架けることにした。橋を架けるといっても、水はまだ恐ろしい音をたてて滝から滝へ流れおちているのである。水は真白に泡立って、今にもその中から言い伝えられている龍が、飛び出てきそうである。それでも旅の人の難儀を考えて、恐ろしさをおさえて工事にかかることにした。 このとき、一人の六部[ろくぶ](諸国をめぐる僧)が、池穴から小井へ向かっていた。雨で荒れた急な坂道を登って、やっと、大矢の谷の見える丘についた。心地良い風が吹いてきて、思わずかたわらの石に腰かけてほっと一息ついた。 汗がひくと、あたりの景色が落ち着いて見えてきた。大水の音がゴウゴウと聞こえる。谷は泡立ってところどころに見える岩は、飲みこまれていくようである。水のいきおいにおされるように、目を下へ下へ移してゆくと、村人が何人も大騒ぎしているのが見えた。どうやらこれから歩いてゆく道の橋がおちたらしい。その橋を架ける騒ぎのようだ。 「わしら旅の者のために、村の衆が難儀してくださるのか。ありがたいことじゃ。」 心の中で念仏を唱えて、じっと工事の様子をながめていた六部は、はっとした。 なんと、一匹の龍が、丸太を引き上げている村の衆を、そのヒゲで助けているのである。丸太を組み立てている人の足場は、龍の背中である。まるで龍と人間がお互いを知り合っているかのような作業ぶりである。しかし、村の衆は、龍の力を借りていることを、まるで知らないようだ。 六部は、ひどく胸を打たれた。「なんとありがたいことじゃ、なんと信心深い人たちなんじゃろう。」 ぼうぜんとしていた六部は、われにかえって山道を下っていった。念仏を唱えながら……… 工事の現場は近くで見れば、ますますおそろしい。大矢の谷の水はまるで天から落ちてくるようである。水煙が雲のようである。龍のウロコのひとつひとつがはっきり見える。村の衆が、龍の背中に載ってかけやを使っている。トビで丸太を引き上げる。その男衆らの腰に、龍はヒゲを巻きつけ、転落を防いでいる。龍の目は、なんとも言えず優しげである。 村の衆は、手を上げて六部に橋を渡るよう合図した。六部にとって、この村の衆までが仏の使いのように思えた。 六部は、峯越[みねのこし]の森屋にたどりついた。そこで茶を飲みつつ、語るともなしにそこのばあさんに、 「今日は、大変いいものを見せてもろうた。」 「実はな、さっき通って来た谷でのことじゃが、村の衆が龍の背中に載って橋をかけておった。」 「へェー、そんなことがあるかねー。」 「いや、村の衆に見えなくとも、わしの目には見えるんじゃー。村の衆の引っぱる丸太へ、ヒゲを巻き付けて手伝うていたんじゃ。またな、落ちそうな村の衆の腰を、しっかりヒゲで巻いて転げ落ちんようにしておったんじゃ。なんともありがたいものを見せてもろうた。まるで夢のような光景じゃった。」 六部は、夢からさめるのを惜しむかのようである。 「そりゃ、もしかしたら男滝[おんたき]さんかもしれん。男滝さんの主[ぬし]は、昔から龍じゃちゅう話じゃあからのー」 と、森屋のばあさん。 「そうだろうなあー。」六部はつぶやいた。 夕方橋を架け終った村の衆が、森屋までもどってきた。全身ずぶぬれの男衆らに甘酒をばあさんはふるまった。ばあさんは男衆らの帰りがけに、さっきの六部の話をもちだした。 男衆らはびっくりしたようだったが、すぐ笑った。 中の一人が、 「確かに六部は通ったが……けんど、わしらは岩にのぼって作業をしたんじゃ……まあ不思議な話じゃが……」 「もう一ぺんもどって見ようらよ。もし龍が助けてくれたんなら、あの岩はないはずじゃあー。」 それもそうじゃ、ということになって、三、四人の若い衆が道を下っていった。外の者は、また茶屋にもどって、若者たちの報告を待つことにした。六部のことやら橋のことやら、大矢の谷の言い伝えのことなどが話題になった。 やがて、さっきの若者たちがもどってきた。一様に若者たちは青い顔をしていた。急いで来たばかりのせいではないらしい。 「どうじゃった。」と一人の年寄りが、心配気に声をかけた。 「ない、ないんじゃ。」 「何が、なにがないんじゃ。」 「さっき足場に使うとった岩が、全部ないんじゃ。」 「橋は。」 「橋は、ちゃんとかかっとるよ。」 そこまで聞くと、みんなは橋へ向って走り出した。 まだ半信半疑なのである。 ゴウゴウと流れおちる大矢の谷-その橋に集まった村の衆は声を忘れた。自分たちが足場に使ったりした岩は、本当にないのである。あるのは泡立って流れる水ばかりであった。 一人が手を合わせた。それにならって、そこにいあわせた者全部が、静かに手を合わせた。まるで、足が地についてしまったかのように村の衆は、いつまでも祈っていた。 |
||||||||
|
||||||||
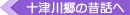 |