
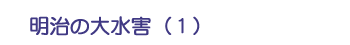

 明治の頃には、わしらの宇宮原[うぐはら]は五十戸あまりもあって、たいそう繁昌していたという。在所の宝蔵[たからぐら]には競馬場(八丁[はっちょう]競馬)があったし、造り酒屋もあってにぎわったらしい。わしらの祖父は、この造り酒屋で働いていたから、暮らしも悪くはなかった。川向こうを西熊野街道が通っており、在所の真向かいにあるきじ矢谷には、旅籠[はたご]があって、いつも何人かの旅人が泊っていた。 明治の頃には、わしらの宇宮原[うぐはら]は五十戸あまりもあって、たいそう繁昌していたという。在所の宝蔵[たからぐら]には競馬場(八丁[はっちょう]競馬)があったし、造り酒屋もあってにぎわったらしい。わしらの祖父は、この造り酒屋で働いていたから、暮らしも悪くはなかった。川向こうを西熊野街道が通っており、在所の真向かいにあるきじ矢谷には、旅籠[はたご]があって、いつも何人かの旅人が泊っていた。ところで、明治二十二年八月十八・十九日の二日二夜、ちょうどほそびき(直径一センチほどの綿ロープ)ほどもある大雨が天から落ちるような勢いで降り続いたらしい。 その時、旅籠には十二人の旅人が泊っていたのじゃが、その中には、その頃の宇智[うち]・吉野郡長玉置高良[たまきたかよし]さんもいた。 「こんなすごい雨は初めてじゃ。こりゃ、きっと何かがおこる。たいへんなことになるにちがいない。」と、もう九十歳にもなる宿の年寄りが、さも心配そうに空を見上げるのじゃった。 「なあ、みなの衆、これは危い。早よう山へ逃げよう。」と、うながすが、だれ一人として相手にしなかった。年寄りは、仕方なく一人、降りしきる雨の中を山の頂上めざして登りそめたのじゃった。 年寄りが、山の中ほどにある松の大木の根元にたどり着いたときじゃった。いきなり、大地をゆするような地ひびきがしたかと思う間もなく、足元の山が崩れ落ちていく。真下に見えていた旅籠がぐらっと動いたかと思ったら、山のかたまりといっしょに荒れ狂う十津川の濁流に水煙[みずけむり]とともに呑まれてしまった。それは、あっという間のできごと、山肌がえぐり取られ、木立ちも家も消え、あたり一面が明るく開けたようじゃった。 このきじ矢谷の山崩れで在所の家々がいくつも流された。 この年、わしらの父は十七歳。母はまだ十三歳じゃったらしい。 川の水が、みるみるうちに上がってきて、今にも家がつかるというので、外へ跳び出てみれば、水はもう膝上までもきており、命からがら上の山へ逃げたという。みんなガタガタ震えているところへ、川向うの上野地から矢文[やぶみ]が飛んできた。矢に結びつけられた手紙には、「川下の丸瀬[まるせ]に大山崩れがおきて川がせき止められた。今、中野村[なかのむら]じゅうが湖になった。」と、書いてあった。 そういえば、流れは逆になって、十津川は大塔村の方へと流れていく。水かさは、いよいよ高くなるばかり。やがて、第二の知らせで、宇井や辻堂までも逆流しているということじゃった。 何軒も何軒も家が流れる。波間に浮いたり沈んだり、やがて水煙の中へ消えていく。分家の為五郎[ためごろう]伯父[おじ]が、流れる家の屋根にまたがり、泣きながら手を振っておめいた。「おれはもうあかん。お前らもっと上へ逃げろ。」 為五郎伯父は、みんながわなわな震えて見守るうちに大波に呑まれていった。 一度、へりはじめた水は、また増してきた。どこか山崩れがおこったのか。この水で、祖父の家もとうとう流されてしまった。 宇宮原は、殆どの田んぼや畑を流し、山林を荒らし、道をとられ、人びとは途方に暮れた。 祖父たちが、流された家をさがしていたら、五粁[キロ]ほども川下の、林の在所まで流されていたそうじゃ。祖父たちは、何日もかけて家道具[やどうぐ]を拾い集め、かもに組んで宇宮原まで引き上げてきたということじゃ。今、わしらが住んでいるこの家の奥の間の六じょうは、そのときの家道具を使って建てたものじゃ。 大水害があってから、きじ矢谷を郡長谷[ぐんちょうだに]、または郡長ぐえと呼ぶようになったということじゃ。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
 |