
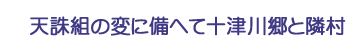
| 玉置口に在りし紀州の検問所のことは、既に述べたり。北山村小松あたりの備へとしては、通行を止め食料買ひの十津川人乃ち當地人は封鎖して入れなかったやうだ。木を切り倒し道を塞ぐ。その傍ら團体組織内部を掌握し守ってゐたらしい。十津川郷はこのやうに完全に戦略的に遮断、封鎖されてしまってゐたのである。 南熊野の辺り、乃ち今の尾呂志あたりは成務天皇の頃まで、完全にそしてその後も不規則ながら十津川領となってゐたが、徳川期前後に至り紀州領となってゐたためにここにも天誅組を容れぬ軍備があった。この辺の穀倉地の尾呂志なれば無理もなかったらう。 今でも殘ってゐるらしいが、當地の名代の風傳峠の險を厄して之に備へたるらしいが、堆く岩石の類を道上の山に集め上げ、戦のときは千早城戦法にてこれを投下し、攻撃せんとしたらしい。天誅組の方は終わりに降伏であったが、最初のうちは東野の上部に石火夫の台地を作り、例の木製の花火筒の如きを備へたと云ふ。一度恐る恐る弾丸(丸太の切りしもの)を入れ、尾部の穴に煙硝を置き、槍の先端に艾(モグサ)を取り付けて火を点じ發射したるに、立合川辺に飛んだのが見えたと云ふ。その真剣な顔色を思ふ。然し之を當時の人の生活より考へると少しも笑ふ要はなく、何百年の後には今の新兵器も笑はるる時がないとしない。現に16~7年前の大和など威を誇りし大艦巨砲も飛行機の威力の前にはスクラップ化してしまった如くである。又、木製砲も笑ふべきでなく、長州は外國軍艦の砲撃に敗北したが、明治建軍の祖と云ふ大村益二郎の軍艦は、艦が沈んで大砲が浮いたと云ふ話がある。これは木製であり疑似砲であったからである。然しその心の壮なる、知識慾の旺盛なるは賞すべしである。又日露戦争頃の旅順攻撃には優秀な大砲もあったが、不足し木製のものを以て威嚇したらしく、その数280砲と云った。又、我々の小学生の頃、日独戦膠州湾攻撃の際、独軍が砲も人も木製にて威したることあり。正義の戦術もなかなかにして、何と云っても當時の人の一事一長の努力が分かる。 扨て、天誅組の変の當時、有蔵では鎖鎌を持ち緋縅の鎧着た東中の小平と云ふ人が通行人を取り締まってゐたと云ふ。(幕府軍の)本流は萩又は龍神筋に備へあり。(首領の中山忠光)一行は、初め南下して海に出るべく構へしも、(道が閉ざされたため)やむなく北山を経て脱出するほかなかったらしい。そして鷲家口の井伊勢突破となるのである。 |
||
 |