
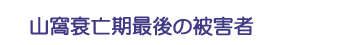
| 我幼時の頃、川原乞食と云ふもの多かりき。最後に見しは下北山桑原にてこの村の医院に在る時、夫婦もの鰻などを賣りに來るを知る。我17歳位の時なり。この川原乞食は、我今考ふるに山窩の衰亡期で一般民へ隠れる移行期と知るなり。 セブリ(瀬降)の在る川原を見たり。暫くではありしかど、今之を知る者僅かなり。島津、瀞では青石と云ふところで2~3群でセブリを張り、川魚を捕って生業としてゐたらしい。 夏はかうして生活し、冬はクマシダで籠作りや箒作りをして賣る。今我家に食器用の籠あり。強くしてよく堪へ、何十年にもなるなり。我は、當時之を賣る老人の姿も知ってゐる。言語も少々変はってゐたるに殘念ながら、今覚えなし。之は然し眞面目な一族にして、冬は盗賊をなす乱暴組もありたり。 日本の歴史は一般的に悲惨な生活に終始してをり、今でも九州南部、日本海沿岸には生活の故に人を害さねばならなかった歴史と風俗、言語が殘ってゐ、太平洋岸にても愛知、静岡、日本海側では青森、秋田、石川、福岡など幾多あり。信州あたりを中心として全国山村に山窩と云ふ特殊な異色あるグループ在りし。この地も斯のごとし。 扨て、山窩衰亡の移行期とも云へる時期に最後の大被害を蒙りしは我家なり。決して普通の賊に非ざりしなり。茲に記す。 我父菅尾より分かれて家を持った僅かの間のことなりき。我産まれて1歳の時と云ふ。母の實家は小川口に在り。我母と共にその實家に帰りしある日の出來事と云ふ。その頃、新宮通ひの和船を杉岡直吉令兄浦地が経営してをり、當時は家の事情で我家はそれに加はってゐなかった。ほかに東善二郎兄弟、平作市父子ありて運輸のことに當たり居れり。我家は折ふし家屋改造のため屋根職人、杣人夫(榎本清太郎氏外)、大工弟子ども、我父、店の番頭(入鹿の西増正介)、女中すべて家に在りたるよし。當時の金庫なれば粗末なるものなるべく、数ミリの鉄板と砂などに木を加工したる金庫あり。重量は25貫と云ふ。この中に當時(明治38年)としては、父の大金たる600円と證書類そして母の實家より預かれる(母の實家は元大なる酒屋にて在りしも當時は滅亡の淵に在り)五両、一両、二歩金、一朱金その他銀類など古金銀預かりありしと云へり。我家も隆盛に向かへるらしく見へしなるべし。上り下りの物を扱ひ日常の品を賣りしと云ふ。 ある朝のこと、番頭第一に起き出でたり。職人の多くは前夜の集ひの酒に堪能して熟睡しゐたりと云ふ。番頭(今朝は寒く指凍へて充分書けず)ふと氣のつけるあり。店の正面戸二尺余り開かれてありたり。心に、直吉船夫本日下新の筈、朝早きの約束なれば注文その他立ち寄る打合せありしにつき、扨ては同人來たり、施錠忘れありしため開きしならんか?、と考へたりと云ふ。(この頃より船夫は2尺×1.5尺×1.7尺位の船櫃へ食料・帳簿・衣服一切を入れ居たり)然し念のため、その戸を検せしに豈計らんや錠(と云ってもサシコミのもの)の横を菱形に手の入るだけ見事切り取られあり。かくて大騒ぎとなれるよしなり。薄い杉板、鉋をかけしもの、営利なる刃物にて切れば容易なり。 直ちに父の寝所に至り之を傳ふ。布団を敷き、平常は金庫に頭して寝るに、この日に限りて足位にて寝たり。机あり、その上に金庫、その上に煙草の入りたる杉箱(長さ3尺、高さ2尺余り)を載せてありたり。 賊は、その箱をとり、父の布団の上、足の上あたりに載せありしと云ふ。丸太の4寸ものを持ち來たり、我にて求めし(偵察だったか)大き麻縄にて金庫を持ち出す荷造りしたるやう、布団その他に点々と附きたる足跡にて分かりしと云ふ。賊はかくて目的のものを奪ひ出し、さて川を下らんか、橋を渡って山越しして逃げんかを考へしよし。追手を憂へてのことなるべし。そこで先づ今の組合のあたりに小さな倉庫あり。ここには預かりし米、酒、味噌その他あり。この戸を破りて中に入り、酒4斗樽の横に穴を穿ち之に口をつけて互いに酒を吸ひ、傍らの味噌樽を破りて之を嘗めて肴とし、相談したるらし。 初めは山を越えんとせしか。4斗俵をヒ首にて切り放ち、米2斗余りを奪ひ、袋に入れて去る。さて、人々大騒ぎの中にて、いよいよ賊の難と知るや、金庫が我家の盗難であり、次が菅屋の右倉庫内の難なり。 いろいろ物色中、今の駐在所にありし古き納屋の戸前に積みありし杉皮の間に差し込みありし屋根屋の鋭い庖丁がなく、之により戸を切りしこと、かくてはよほど以前より偵察、事情を知りありしこと判明す。賊は米袋の一隅に破れありしを知らず持ち出しし故、彼らの通過せし路上に線を描くやう米粒落ちてあり。米を辿り行くと現ホテルの眞向かふあたりまであり。ここにて立ち止まりたる形跡あり。而て引き返したるやうなりき。 實際引き返したり。金庫25貫もあり。山に隠るるも容易ならざるなり。返り來たりて川辺に降り、船を奪ひて逃亡せしなり。この頃、木津呂の人ら來り云ふ。この日の午後、瀞の野にて5人余りの男、ふざけ遊びゐたるを見しと云ひ、上方より見ると一隻の舟、岸に見たりと。さてはと驚きたるらし。田戸側の舟1隻不明なればそれに相違なしとなれり。父もその前日あたり店に居りしところ、一人の見知らぬ男來り、キョロキョロ内を見廻しての末、あれを欲しいとて例の麻縄を男ひて去りしと云へり。ここにて思ふは、もし父が声を出したるならば一刺しにて殺さるべく、又もし之を氣づきて知らぬ風して舟にて逃るる途をこちらより総員して追跡すれば、こちらに鉄砲もあり、何の造作なく捕らへ得たるにと殘念がりたるらし。ともかく瀞入口の川原へと急ぎ行き人々の調べしに、果たして山に寄りたる砂地にて金庫破壊したるなりき。例の屋根屋の有せし強鋼鋭利のものを用ひ、石を槌として之を破り、箱を取り出し、通貨、古金類は金のみ、銀は捨てあり、證書類はこの上にたたみて風に散らぬやう古銀にて押さへありしと云ふ。 勿論、警察取り調べも杳として風の如く、手の施しやうなし。取り合へず新宮、木之本あたりの各署へ手配したりと云ふ。 凡その見當も南方へ逃げたるは間違ひなしと断定せしなり。 一乃至ニケ月の後、木之本署より當署へ連絡あり。鬼ケ城(そこに當時山窩の流れが多く屯し住みゐたる)の乞食の群は、この頃一円、五円などの大金を費消するものあり。乞食にしては不審多ければ、近日の内急襲して一網打尽とすべきよしとありたり。然るにこの計は未然に洩れて、手入れの時は首魁らの逃げ去りたる後なりしと云へり。 次いで四ケ月過ぎし頃、新宮署より連絡あり。串本の先、袋港に乞食の群多し。その内に金不相応の所持者あり。近日手入れする旨なりき。 新宮署は、刑事二名余りの劣勢なれば、拳銃を持たせたり。二人の刑事、急に入り逮捕せんとするや俄然抵抗する者あり。追へば後方の者迫り、後方へ向かへば先方の者迫り來るなどにて大苦戦したるよし。遂に一人の頑強なるを捕らふるより射殺を決して拳銃を撃つ。痛手のために賊は狂ふばかり逃げたり。他は恐れて遂に降る。後刻道を探し行けば、現場より4町余り離れしところ、道の傍らの雑草木に腹部を撃たれ朱に染みたるまま死せる一人を發見せしと云ふ。ここにて捕らへたる内二名が我家に入りし者にして、他はその疑ひなかりしと云ふ。いろいろ取り調べの結果、死したる者は首魁にして四國徳島県の者、あと一人は新宮権現山川原にありし者、もう一人は不明にして名も不明なりき。 その後3年経し後、奈良市にて二名捕らへられ、殘り二名は天網を逃れしなり。 |
||||||||
|
||||||||
 |