
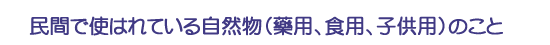
| 今は大分形勢が変はったが、一部にはまだまだ自然物を昔からの経験で使はれてゐることを一通り記しておこう。 藥用より始めると、熊、猪、猿、狸などの胆嚢、つまり「イ」である。少ないが鹿茸(ロクジョウ)もある。これらを最重要物として、他に金品的価値も賣買もないが牛の角がある。 クサギの虫、臭木の幹に潜むカミキリ虫の幼虫で、太いもので指位ある。虫は日光を受けないが日光の作りたる繊維を喰ひ、丸々と太りたるをとり焙りて子供の疳の藥として与へたものである。之は然しビタミン源の補給としても栄養としても、信州のやうにヘビ、蜂の仔を喰べない當地としては良いことと思う。動物の「イ」の如きは藥理学的にも意味があり、その應用に當りては病症を考へて適するやうに与へなければならぬ。なお「イ」は病ならずとも与へるのは良いことだと子供に飲ますことにも意味がある。永年の経験からの知恵であって一驚するところなり。 ハンビ(マムシ)を焼酎に漬けて之の液を飲んだり、またハンビの皮をはぎ焙りて喰ふ。病人や体の弱い者には、効ありとする。なお、之は都会でも行ってゐる。 「三間トビ」と云ふ蛙をとりて子に与へたり。時には山椒魚と云ふハンザキの一種の5~6寸のトカゲ様にして、谷間に匍ふものをとらへ、ハンビと同じく焙って食したもの。(三間トビも同様。) 今は全くなしとするも、父ら幼時の頃は百足(ムカヂ=ムカデのこと)を食する者もゐたりと云ふ。尤も昭和初期(或いは今もあるか)に百足を瓶に漬けて油をとり、切り傷にそれを貼ったものである。また、アメノウオの油を耳漏(ミミゴ)の耳孔に入れたりした。良いことと思う。 我々には、少し合点の参らぬものもある。ハンビの皮を腫物(フルンケル・カルブンケルなど)に貼りつける。ヘビの卵を飲んだりハンビの胎仔を飲んだり、或いはこれらの黒焼きを作り、粉にして食したり、病人の強壮剤とした。啄木鳥の黒焼は、肋膜炎に良いとて用いられ、ウグイスの卵黄を日本紙に付着せしめて保存し、眼を傷つけし際、之を用ひたり。又、乳の出る藥として鯉を食べた。 ヘビの抜け殻(脱殻)を疣(イボ)の藥としたり。茄子の漬物二分して疣をこすりそして(その茄子を)二つ合わせてワラにて括り、人の知らぬ処へ捨てる。歯の生へ代はりの時は、牛の檻(オリ)に至りて、良い歯が生へるやう(古い歯を)投げたりした。かうなると完全に咒詛と重なってくるが、その願望の發展が面白い。 動物も(藥として)限りなくあるとして、植物の方では刺さりたる「トゲ」を抜くにホウセンカの實を黒焼として飯で練りて貼る(キジ=雉の足も用ひられた)。化膿を促進して欠潰せしめるには、ゴバウ(牛蒡)の實を飲んだりしたものである。 シュウサイまたは重藥と云ひ、解毒の意味であらゆる病は煎じて用ひられた。ゲンノショウコがウメズルと云はれ、乾して蓄へ、腸の病に用ひられた。 今はあまり耳にせぬが、猿の頭(首より上)全部を赤土にて外部を塗り固めてボール状として、焚火にて焼き黒くなりしを取り出して脳の藥として、その粉末を用ひたものである。これらは、例の信仰のやうに扱はれたものと思ふ。然し、黒焼粉末は吸着剤としては効あり。 ミミズは漢方藥に示さるるも、あまり用ひられしを知らず。熊の如き皮は装用とするほか、肉も内蔵も脂も藥とし應用されしは山の王者の故か。貴重であったらしい。(例えば)熊の腸は乾燥して保存しておき、病のとき飲んだものである。 猿の塩ベシの如く羚羊(カモシカ=ニク)の胎児などを塩蔵し、味噌汁に入れて用ひたことも多い。我田辺の中学生の頃、下宿の藥屋へ客あり。心臓病であるが医者の藥が効かぬと云ふ。猿の心臓筋肉の塩ベシを賣ってくれと、云ふ。我主人に代はりて壺の中を物色するも見当たらない。然るに主人來りて猿の肉の一片を客に賣りしを覚えてゐる。皇漢藥を賣る店はかくて儲かったと云ふもの。 蜜もそのまま、又は酒と配し或いは湯を加へたり、他のものと混ぜて練藥として用ひられた。最近もローヤルゼリーの説の如く貴きものである。 鶏の卵酒と云ふものをよくやったものである。卵は栄養の高い食料であるが、風邪のときなど酒を?燗して卵に加へ、掻き混ぜて飲みしものである。或いはツケ木(点け木)などに火を点け、之を卵に注ぐ酒の中間に置きて燃へ上らせ(アルコール)て混ぜるものもあった。淡竹(ハチク)の中に卵の中身を入れ、火にて加熱して之を弱い子に喰はせたりした。 ニラを強壮剤として食べ、古い所ではシソの實を催経剤としたこともある。最近はニンニクが多くなった。ニワトコをリューマチなどに用ひたが、茯苓(ブクリョウ)の元なるマツフドは一般的でなく、何かの知識があったやうだ。バベ(ウバメガシ)の皮、栗柴、茶、樫、椎の皮など、そのタンニンの収斂性を利して皮なめし以外の民間藥として湿疹その他の罨法(アンポウ)剤として用ひた。 センブリ(千振り)の苦味は胃病の人に用ひられ、ハモゴレ(馬酔木=アセビ)の葉の煎汁は、牛のシラミ取り。山椒の皮、トコロなどは旱天の一種のレクリエーションとしての川流し、つまり毒を小川に放流して小魚、ウナギなどを得るに不可欠のものであった。少し古いが天南星(ヤマコンニャク)は、便所の虫殺しとして用ひられ、商陸の一種ヤマゴボウは、盗汗(ネアセ)の藥として用ひられたが、これは極めて難しい。中毒を恐れたものらしい。 葛根、ワラビ、百合根も食用の意味と藥用の意味で用ひられたが、吉野方面では商品となるのに、(當地では)あまり大したことはなかった。 ウロネと云ふカラスウリの根の澱粉は、主として賣り渡された。然し最近30年は全くなくなってしまった。山の芋も同様藥食に用ひられたが、今は珍物としてのみ食用となる。一つ葉の黒焼を油で練り、瘡に外用された。大字高瀧の火傷の妙藥とて、昔は重要視されてゐたが、これは我の考へるところ、松の薹、杏または桃の仁、キツネの小便壺を粉末として、麦飯の痂皮にて練りたるものなり。第一度の火傷には確か効あるも、それ以上は効なきやうであった。かえって不良の果を招きしものもある。 食用としては、山の芋、虎杖(ゴンパチ)の芽、ワラビ、ゼンマイ(之は商品価値もあり)、茸類は申すも及ばず。臭木の芽(之は煮て陽にて乾かし、大豆などと炊くと美味なもの、如何にも山の味あり)、タラの芽、ウド、樫の實、曼珠沙華(オイモチ)、この内樫の實、曼珠沙華は食料欠乏の時代に多く現れる。そして技術を要する栃の實、これは昔は重大なるものにて、食料として保存も効くし、栃木証文と云ふものある位であった。その渋を抜く、そして食料にするまでが大変である。今でもやはり下葛川あたりでは餅として用ひる。尾鷲には戦前よりトチノアジと云ふ名物を駅で賣ってゐた。 とにかく、あぐればまだまだあるが、いろいろ工夫して喰べられるやう(毒まで抜いて)に我々の祖先は食料に充て、又は具へてゐたと云ふことは立派な郷土文化の一つであり、昔からの如くならば我等の明日への目標を与へてくれ、自分の位置を格付けてくれると云ふものである。 五穀の中、稗はこの地方ではあまりなく、昔西川あたりにては万一に具へて保存して置いたらしい。一度試食したこともある。美味しいとも普通の方法では思はない。拵へるのも稗の粒が細かいので大変であらう。然し、栄養上は米以上と云ふことである。 茸類の中、椎茸は今も昔も輕くて高価で珍重されるものであり重要な財源である。経営的で恒久的である。 子供のものとして喰べられしものは、松の寄生木のカラスノツギキの實、サセンボの實、桜の實、桑の實、皐月の花瓣、皐月の葉の膨隆せる(實は虫の巣)もの、虎杖(ゴンパチ)、山栗及び椎の實、アケビ、山柿の熟れしもの、稀にスイバ(カ夕バミ)などであった。口を黒くしてサセンボの實、櫻の實、まるで猿の如く木に上ったことを覚えてゐるが、懐かしい。子供の喜ぶ山の喰物としてしまへば何ともないけれど仔細にみると益もあらうが害もあったらう。山野で採れたこれらのものは、都市から入ってくる必要素の何か欠けた、歯を不良にする菓子よりずっと良かったと思ふ。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
 |