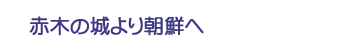|
|
|
|
| |
赤木城のことはどうしても他人事としておいておく訳にはゆかない。津久一揆(北山一揆)の時も、十津川は必ずしも無関係でなく、又當時の十津川領土の下流、入鹿あたりへの関係もあるからである。
赤木城主藤堂佐渡守の頃、秀吉の朝鮮征伐あり。出陣の命にて出征したと云ふことである。一、槍 三本・一、鉄砲 二丁・一、大提灯 三・一、小者 三とある。今からみると噴飯物の大出征であるが、よく考へると天下様秀吉の一顰一笑がよく行き届いて、あの赤木の小城にまで及んでゐたことが分かる。尾呂志の長徳寺でも我は當時の尾呂志陣屋の出征したこと、並びに分捕品と云ふ朝鮮茶碗、軍旗を見た。 |
|
|
|
|
|
| 注- |
赤木城跡-三重県南牟婁郡紀和町赤木 |
|
天正13年(1585年)頃、藤堂高虎によって築城された。赤木は熊野北山郷十津川郷などに通じる要衝で、城は本丸、二の丸、三の丸、馬場、堀などを残し特に整然とした石垣が目につく。城跡から西方700mの地に田平子(たびらこ)というところがあるが、ここに藤堂氏が罪人を晒し首にした獄門場跡があり、「いったらもどらぬ赤木の城へ、身捨処(みすてどころ)は田平子じゃ」という古謡が刻まれた供養碑が建っている。
藤堂高虎は、幼い時熊野新宮に来住し、成長後、土豪色川氏と共に那智山衆徒を助けて戦功をたて、豊臣秀長に仕えた。天正13年、豊臣氏の熊野征伐に際しては、一方の大将となり、ついで秀長の命により羽田(はだ)出羽守と共に奥熊野の北山郷・西山郷・入鹿庄などを支配する代官として検地を励行、いわゆる北山一揆を勃発させたが、これを手際よく鎮圧した。文禄の役、朝鮮出兵には鵜殿村で軍船100艘を建造し、熊野水軍を配下におさめ、その先陣となった。
関ケ原の合戦後、一時奥熊野を統治したが、庚長19年(1614年)北山一揆が再発すると赤木城を補修し、その鎮圧にあたった。この時の処刑者は300余名という…………
山川出版社「三重県の歴史散歩」による |
|
|
|
|
|
|
|