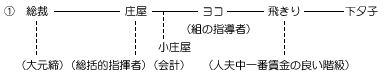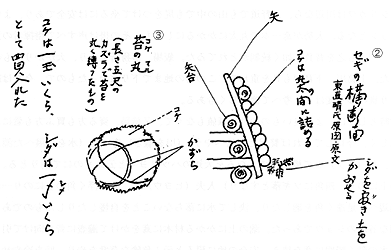| 道路が荷車道、木馬道、そして今のトラック道になるまで、この葛川谷奥地よりの木材の搬出方式は、昔より小川を主なるルートとしてゐた。然し水量も少ない、岩の凹凸が多く場所の悪い小川は、特に當時は(材木の)太さの好みありて、そのままでは流下しない。資本を持つものは誰でも出來たが、多くは山も出材の資本も他所の大物に限られる場合が多い。出材は多くは請負業であったらうが、後處、此處より大勢の人夫の群れを集め、請負の主は絹物を看て旦那風、(組織は)総裁とかヨコ庄屋、横、飛切とかの階級を能技により定めて、川の瀬の處々を材を利して堰止め、岩を割り水を湛へて、大量の木材を投じて、木遣り掛け声面白く、鳶を打ちて流送する。第一線のヒヨウ(日傭)の風は、手甲、きゃはん、信州袴と云ふ野武士のタッツケ(裁っ着け)に似た膝より上はダブダブのものを履き、足袋、草鞋で手拭鉢巻で元気よく唸りながら仕事をしてゐた。腰には鉈と云ふやや厚味の包丁を中途で切ったやうなものを(腰に)帯びて、獣の毛皮(毛のつきたる)1フィート四方の尻革(シリカワ)と云ふものを色を交へたる紐にて尻にぶら下げてゐた。このシリカワは川辺なら、又野道でも山の中でも尻をつけて坐るには安全であり、よいクッションとなる。大勢が鳶一本で丸太にかかるにしても、その掛け声すべて指揮者の意の如く、囃子も之を背負ふ如く統制がとれてゐた。飯場、事務所もあり、大がかりなものもあった。上葛川、下葛川も日を重ねて、この瀞の地まで下り來たったもので、今では珍しいより世の移り変はりを考へて懐かしくもある。 當時としては、より良いものの外は価値もなくて、又結局、賣る方も買ふ方も量において□しく、今にしてみれば贅沢とも云へやう。(川を堰ぎ)青々と(水を)湛へた淵をつくり、角(カク)とて樅、栂の大なるを大斧のハツリヨキと云ふものにて削りとる。(材木の上にのり、四角にソギ落とすなり)人夫(ヒヨウ)は、よく浮く角の上にのり一辺より他辺へと足速く角を廻したり、決して水に落ちないことを自慢したりしたものである。長閑な谷川のショウであった。瀧の上にかかる材木に鳶をかけて瀧壺に背を向けて引っ張り、木の動く瞬間に鳶を抜き、安全の地に戻ると云ふ危険な芸當をやり、肝を冷やせしもの。(十津川あたりでは、萩から一本の木材にのり、鳶にて平衡をとり新宮まで下った者もいくらもゐる。)また、立木の下にゐて鳶を打ち込み、桿を傳って上り、外して落ちぬ前に又上方へ打ちて上ると云ふ千番一番の曲芸家もあった。確かに當時の人は運動神経も筋力も三半規管の機能も優れてゐたかも知れぬ。僅か45年間に、その個々の能動性は確かに変はった。 村の人は、徑尺位の「苔の丸」と云ふを作り、(親方に)買ってもらったものである。これは、堰(セギ)の場合のパッキングによいからである。 (人夫は)信州あたり、又中辺路方面より大勢來りしものであると覚えてゐる。大体、この地方の人は、昔から団結行動を自家経済の上で示し、十津川あたりは意味が変はり、政治的に団結してゐたやうであることが、この面にも現れて來る。一方は田を有する、又は良い地であるが大名の苛政あり、一方は山國で人並みの生活をするには、やはり時の権力ある政治家と結び、由緒とか例とか故實とか格式とか、歴史的により多く強く働きかけて稼業のみならず中央へも近づくべく努力したものである。面白いことなり。 |
||||||||||
|
||||||||||
 |