
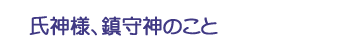
| 日本は、全國的に各村も町も部落も、平坦な地も山もすベて、氏神とか鎮守ネ申をもち、各地それぞれの神樂、獅子舞、踊り、投餅、神輿、神与のものの奪ひ合ひ、果ては喧嘩祭りなど様々ある。山車の豪華を誇るもの、連日の行列や歌、挙げて数ふべからず。 尚、戦後不滅にして、却って盛んとなる。米軍の妨害にもかかわらず、儀式的な神事に熱中するさまに異様なくらいである。ここには原水爆の極端の科学もない。期日を決めて年々歳々行はる。大なる神社などは、第二次大戦後、皇室中心・軍國主義の温床として厳しく弾圧され、収入減にて衰弱せしも、またまた再燃し來る。如何にクリスマス、ジングルベルの時代と云へ、之を忘れない日本だ。 小さくなった日本は、發掘・調査・改築・復元・指定等いよいよ盛んであるが、當然である。日本人の宿命は絶対に不変であること、運命は多少は改めることが可能でも、これは致し方もないし、日本人であることの誇りは、悪かった面もあったらうが、これより外なく、その傳統を保ち、よい面を守り立てて行くことが、これからの日本にとり、實に大重要事であり、それには發掘・復元なども同類のものである。 明治20年頃、神道は宗教にあらず、祭典の行事なりと云った人がある。人の生活や社會にまで入りこむことの少ない、ただ崇敬し奉るとのみで救済なく、宗教でないと云ひ、単なる祭典の行事と云ふ意味であらう。そして、神官は形式的で僧侶に劣り、内容はカラ(空)と云ふ。然し、頭はカラッポでもよい。一蹴してしまう理由にはならない。外人が証明してゐるし、第一最古の文・記・紀以上の祝詞をよく読み、怪しみつつ日本とギリシャ神話とは世界の双璧と云はれしを熟読すると分かり、ここに日本永遠の生命がある。 我在田辺市中学の頃、秋ともなれば豊穰を謝し祈り、且つ樂しく集ひする村の青年たち、毎夜の稽古の笛の音、獅子舞を知って、あの景氣のよい脈々たる祭りの前夜に心ひかれ、感心したることあり。また豪華な山車の子どもに大人の群れの美しき風体、武者行列など見て、感に堪へたることを思ふ。 他地方のことはともかくとして、この山中の村には笛の音も神樂の音も聞こへぬが、投餅・祭儀に老若男女集まりて、仮令形式なりと云はれるとも行はれる。そして寺ありとも神社はあるはずで、祭りは行はれてゐる。 祝詞をみると簡単であるが、その當時より喜怒哀樂、また虐げらるるもの、乃ち悪神により實に苛酷な取扱ひを受けたり。非道なことに嘆く人もありたるは眞意にては、個人的に今より以上虐遇されし者ありたりと見ゆ。即ち悪神、荒神なり。善神は之を嘆じ哀れみ、これに一の法(ノリ)を与へ、人の常道正道を示し、悪の追放を示したり。 個人修身制家には、『宮柱底つ磐根に太しく立ち、高天ケ原に千本たかしり』の如く、天津神つまり今の憲法の如き全体を云ふ。『生剥、逆剥、糞戸、畦放、串刺、虫の災い』まで強く戒めたり。生きながら皮を剥がれることは、最近のモンゴル、東チベットにもあるらしい。之を早くも串刺し、溝の妨害、糞尿の汚れをここに取り上げたるは感心する。 また、一般法律に準ずるものとして、『生肌断ち、死肌断ち』のことから、母と子、子と母犯せる罪を戒告し、人倫の大事を唱へたる、また悪の追放の方法など、なかなか少ない語の中に、よくよく出し現れてゐる。これでこそ日本は成り立って來、傳統も日本精神も之を温床として培ひ育ったものであらう。日本國家、皇室の関係から下一般まで、ここに生まれたといっても過言でない。揺籠の民族、初めよりかくなってゐたのである。そして、その眞の温床は神社であり、その庭である。昔の苛政に苦しんだ者も支配者も、この日の解放に相集ひて、この日を樂しみ、喜々として晴衣して、この山地にても甘酒を飲み、餅拾ひを樂しみに親睦を図り、若きも老も幼少もおのがじし団欒の日となり、黒酒に醉ふもあり。餅拾ひに合戦の憂鬱を飛ばしたる若者の意氣溌刺として新鮮なるは、集まりし人々に自ずと傳はる。 前後するが、これより先に対象の神祇は、第一の行事として神官の祝詞、祭祀に、祓ひに始まり厳かにとり行はれる。 次に、つひつひ人まことに人の世の神秘さと眼に見えぬもの、乃ち神の偉大さを頂礼崇める。如何なる君主指導の権者も結局は晴々として絶対の信を得べからずと云ふ訳ならん。執り行ふ人も皆大輪(ダイワ)の一塊と化し、和光同塵の内に大なり小なり日本人的好影響を与へるオオマドヒの場と云へやう。ラフカディオハーン(英人、昭和3、4年頃没。東大教授。日本を特に愛し、神社の祭りを世界に傳へくれし帰化人、英文学者。日本名小泉八雲。松江市に遺家保存さる)が、尤も賞嘆し、これを詩に物語に創作し広く紹介し讃へられしは、日本人としても非常に嬉しく肩身も広いわけである。氏の文章には、常に神社の祭りとマドヒ、団欒、日本の發生を美しく採り上げている。むしろ明治以後の最首唱者と云へやうか。 世は千紫万紅、立派な宮居あるのは祈りする者を支へるもの。然し、それはそれとして、田戸の秋葉神社の我幽かに覚えある祭りのことをくるめ記してみる。神社合祀令ありて、それ以前のことを幽かに知るが、一度三大字の氏神を下葛川に集め東雲神社としたり。その後各地とも遥拝所の議起こり、改めて祠を始むることとなる。折ふし、東直晴、中建二郎、東秀清、我、東一郎その他、石及び植樹・敷地のことなど奉仕せり。写真もあり。また、東藤二郎老人玉置山に在り。本社造營の折とて、欅にて祠を作り、力グツチノミコトと記せる鏡を下さる。後、我京都の元の秋葉神社發祥の歴史を尋ねて吉田神社に至りて幣(ミテグラ)を納めたり。 終戦と倶に東雲神社分霊還り、いろいろ修理建設、設置のもの集まりなして今に至る。我が幽かに殘る元の神社は、太き杉薄暗く茂り石段も石垣もすべて苔むしてゐたり。幟立て本殿の横に拝殿ありて、當番の作る白酒ありて、御供の餅、投餅の外に之を一般に飲まし呉れたり。よほど幼少なかりしか、我迷ひ寂しかりしことを覚えてゐる。 杉岡直吉老かつて日清の役に出征せる時のこと、その妻この宮にお百度を踏み、武運長久を祈りしに石段の辺りにて火の玉を見たりしと云へり。 |
||||||
|
||||||
 |