
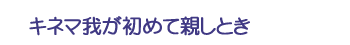
| はっきりしないが、多分入学前のことであらう。キネマの技術は、當時の日本へも來てゐたはずである。今の巡査駐在所の地に菅屋の炭納小屋があった。 酸素エーテルガスとライムの光源。この方法は電灯があるやうになっても、特に炭素線のときは新宮あたりでも行はれてゐた。この方が光度が強かったにほかならない。「ガスが切れました。しばらくお待ちください。」新宮座あたりでも聞いた。全く、今にして思へば、驚くべき光景であった。 今考へると、當時のキネマは、技術も構成も脚色も演出もあったものでなく、短い画面と暗いスクリーンの絵、噴飯ものであるが、これでも當時としては偉大なことであり、矛盾も全くなかった。 ここで思ふ。いくら世の中の文明が發展しても、人の無限の慾望も最初は、この如くかと思ふ。 覚えてゐる。青い画面に白人現れる。悪い人は咎められる。靴の中に入らうとする人あり。靴はそのまま動きだし道を走る。人はこれを追ふ。今のクラブ(公会堂)での映画、映画館でのシネマとは桁違ひのものであった。今は、娯樂用、鑑賞用、教育用、指導用といろいろあって、時間と空間を超越して、昔の再現も未來の予想も、また現在の問題に渡って広く表現活動してゐる。が、然し、この文明の揺籃も、實はかやうな幼稚な技術から胚胎するとせば、顧みて面白い。 |
||||||
|
||||||
 |