
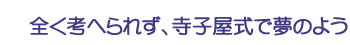
| 縞のもの、紺の無地、とりどりの木綿着物。帯は葬式の旗を使っていたものなど様々。メリヤス少なく、日本式のパッチでもないが、紐つきの縞のあるもの、白地のもの、とりどりのズボン。足袋は專賣と云ふ。爪先の絲でかがった強いものを一としてそれぞれ穴綻びるまで穿く。パンツはなし。小6年頃よりメリヤスのもの現わる。 履物は草履で、破れ易く、雨の降る日はシリバネ(尻跳ね)にて困りしもの。中には下駄履きも雨にあり。更に低い下駄に草履を打ちつくるものもあり。足の強さを示す。 ハンチャと云ひ、紐無しの木綿の上覆を更に着るは凡その人と思ふ。タオルにてほほかむりしたり、教科書は風呂敷に包みて背に負ひ、弁當はワッパ、握り飯。アルミニュームも殆どなし。芋、ナンバ又は「お粥絞り」とて粥を絞れるものあり。「コオリ」(行李)は甚だ少なかりき。紙包みなど千差万別か。之を包み背にするもの、袋に紐をかけるものも非常に多かった。 懐手して話しつつ雪の日も雨の日も、この野蛮生は学校へ。語るもの、その頃流行の浪花節を唸る者、忠臣蔵のその本を手にするもの、「己がじし」行く。上地で極まって口を揃へて遅い友を大声にて名を呼び、集ひて学校へ、又はその家の前に集まりて遅く出て來る生徒仲間を待った。 尋常(4年)ではあまり雪合戦はなく、学校へ着く。そして冬とて土の箱大火鉢で暖をとり、湿りたる足袋など乾かす。その香り今も覚え、當時の感覚の鮮鋭に驚く。遅れた者は、きまり悪げに人の視線を受け、先生の許しで座につく。 (授業の)開始は、壊れかけし鐘を級長が振り、(全員)室に入り先生を迎へ禮をして坐る。 先生は、滋味あり温かなりしもオルガンも弾けぬうえ、音痴の老人(4年迄)。鍵盤に音譜を朱で記しありしを覚えてゐる。唱歌にならない。而し文字などはよく書き、元寇の話、南北朝の歴史をよくした。そして初めて通知簿(綴じたもの)渡されしか。教育勅語、戊申詔書など、之は大切に起立して唱和したもの。歐州第一次戦始まるや青島の爆撃投下の話あり。飛行機の話あり。今思ふと玩具だが、エライものと驚いたもの。 寒い冬は、特に風の吹く大杉では先生は竃に籠もり、生徒に自習させ、終わりになるまで現れない。然し病気の生徒が出ると竃に温もらせ、味噌汁を与へ弁當をとらしめる、放課後は生徒を連れて、店やその他によく出掛けたもの。アメノウオ釣りが好きで、耳漏(ミミゴ)の者は脂を入れてもらった。折りに老先生は、大渡にある我製材所へ薪物をとりに行ったものであった。昔風の人で、少々生徒をエコヒイキしたのも、當時としては止むを得ぬ。この垣野先生は、我等の忘れ難い先生であったが、遂に教壇上に斃れた。 子供の遊びはシンゲキと云ふ、2組に分かれ壘をなし、出でて人を打ち、勝負を決するもの第一で、その他走り合ひ、独楽まわし、パンと称する円いボール紙の上に武将や有名人または飛行機を畫きたる2~3寸位の如きを石、板の如きに載せて、一方がこれに打ちかけて相手の下を掬ふか、帰れば勝ちと云ふ遊びも流行し、終わりにはやや賭博的になり、何かの表紙や型紙を切りて私製のものも出でたり。 ゲンジ(甲虫の一種)と称する昆虫に木馬を牽かせたり、竹トンボ、ヤスリの刃などは私製を誇り、まねしたることもあり。 一年は、ハタ、タコ、コマに始まり、4年では五ケ條の御誓文の暗誦まであり。 外装の□は冬のものだが、夏になると薄くなり、暑くなると共に、途中で水せぎ遊びなど、親泣かせはカラカサを車の如くして走ることであった。洋傘はあまりなかった。 (食べるものといへば、)烏の接ぎ木(松のヤドリギ)の實を、秋はハンダツ(アケビ)を同じく食べたり、サツキ花の類、スイバ、サツキ類の葉に生ずるホクロ(虫の卵あり、刺針により変形す)と云ふものを食べたりした。我は、烏の接ぎ木の實を喰べすぎて下し、不全を起こしたこともある。小豆煎餅を喰べて治った。桑の實、サセンボ、イバラの芽などいろいろの物を喰ひしものなり。桜の實もうまいものは盛んに喰ベた。 習字は普通上塗り型、眞っ黒くなるまで、又は新聞の古、又先生へ出す綴りの清書の古を使ふもの、いろいろあった。 石板にロウ石筆で記した。今思ふと石器時代か。ザラザラのノートも混用。然しノートは上級に多く、下級生はノートも使ったが、石板が多かった。 女生徒につきては頭以外は似たもので、やや赤いものが多かった。髪は毛を括ったものあり。お河童もあったが、本校へ出ると高等科のもの、又大きな者は  型にし、中間の部にタケガワと称する原色の紙のやや厚手の短冊型のものを元結の上に重ねて入れ、後ろにて組み合わせてゐた。 型にし、中間の部にタケガワと称する原色の紙のやや厚手の短冊型のものを元結の上に重ねて入れ、後ろにて組み合わせてゐた。遊戯は鬼とりなど。一人交替で順に輪の中に目隠して立ち、手をつなぐ。外の輪は唱歌を歌ひ、グルグル廻り、停止すると目隠しの女生徒は輪の人物を當てる。當てられると鬼になる。 毬突き遊び、風船遊び。おじゃみとて小さな布に小豆など入れし袋をいくつか投げて受ける。で、毬突きもおじゃみも足を交したり、何ケも連受したり、技巧の面もあった。そして、毬突き歌は、我今忘れたが、古文化ものらしく、前記に少しある如し。 弁當のとき、大きな女生徒はお茶を運び、注ぐ。終わりて食事となる。〔今に変はりて異なる。それでも、食べるとき落ち着かない児もあるために、則夫の3年生位のときは、合掌して「いただきます」としたる由なるも、今はせずと云ふ〕 我児童の頃の教材は、連珠を色とりどりにせし移動式の数器又は枠の針金に三寸平方位の札を付け、桃など記したるを一々かけて数を教わってゐた。算盤は、大黒毛付で、四尺位のもありしも殆ど使はなかった。 先生は、主に袴で洋服も時々着た。児童のメリヤスシャツは然し、ちょいちょい現れてゐた。チョーク、黒板は同じなるも、時々黒板を墨で塗ったもの。然し、黒にいろいろあり。色彩の十分なるものは得られなかったかと思ふ。日露戦争の戦利品として、ナゲシに小銃、速射砲のケースが掲げられてあり、寺内陸相の名文があった。入学も式日も卒業も皆連れられて本校へ行った。新しい、又は一張羅の服、和洋装ひの先生、來賓、生徒たち。主として來賓、生徒は和風であった。白の手袋、礼装の校長がオルガンの音とともに、陛下の御眞影を開扉して、恭しく拝礼、校長に次ぎ來賓、先生拝礼、閉扉。教育勅語、校長訓話、來賓の話など。その粛然たる端正の一挙手一投足、規則ある軍隊式の行動。天長節など今思ふと神威、皇威森厳極まりなかった。唱歌も、「今日のよき日」「雲にそびゆる高千穂の」「年のはじめ」、卒業式の「朝夕親しく交はりて」「蛍の光」など様々。国威厳として帝國日本の礎となってゐた。 懐かしいことである。本校に出た我等は、(珍しい)理科の機具類、校長のみ唄へる(歌)、(校長のみオルガンが)弾けるので、新しい氣分にひたれたものの、然し考へてみると、軍國主義の貧乏暮らしでも、式の日は旭光明らかに、正月などは、道も皆すべて落ち着きのある上に、朗々しく過ごしたものである。 明治天皇御大葬の式には、奉葬の唱歌に困った。「入島の海の空かけて、御□□輝く古き日本」の次より奉葬の詞となる。然して、「あまり高い声では、いかん」と云ふし、(子ども心にも)随分苦心したものである。膠州湾にドイツを敗ったときは、「バンザイ、バンザイ、万々才」と景氣よく歌ったが。 また、大杉の4年単級分教場へ戻る。 あるとき、幻燈があると云って、神下の人、夜をついて列したことがある。何でも2寸平方あまりのガラス板に画いたスライドをラムプの光で(酸素エーテルガスとライムを使はずに)写したものであり、暗くて見えにくかった。但しオルガン(伴奏)は、本校より來てくれたので、今でも耳に殘ってゐる。ただ、音だけであるが。 昨年まで、縣議の堀玉三郎君の父が、ある日、コザコ谷にて仕事中、火を余して一面の山火事となり、大騒ぎしたことあり。コザコ谷、学校の周り、すっかり焼けてしまひ、学校も机など什器を出してあったことを覚えてゐる。 宿題は、夏休みのときなどあり。大抵は、一夜漬けでやったもの。「話し方」と云ふものあり。辛かった。恥ずかしがった者も多かったことを覚えてゐる。これあまり軍國調、皇威八絋調になると考へる。反省の間も与へず、臆病者や何でも行き當りばったりの人間にしてしまう。第2次大戦の軍人と同じものと云へる。 大杉では、4年になる前後、暇あると自然物の遊び、弓矢のほかに、傍らの山に入り樹や竹に床を作って喜んだり、ゴリラのやうな眞似をして遊んだものである。 朝は早く、冬は暗いうち(に起き)、少しでも遅くなると親達によく気儘を云ったものである。鑵子の底を火箸で触り、少しでも早く湧くのを願ったらしい母の顔も思って忘れぬ。我を誘ひくれる東直晴君が咳をしながら下から上がって來、障子を開ける音、今も新しい。直晴君の見より送ってくれしと云ふ珍しいキャラメルや少年世界(博文館)の話、付録の双六など話は尽きぬ。 双六も戦争色で、歐州戦争の画に終始してゐた。飛行機と云ひ、ニューポール式、砲身後座式、軍使やスパイの目隠しなど、いろいろあり。雑誌も主として軍事物、特に爆弾投下、偵察、スパイなど,それぞれの冒険小説があった。押川春浪の作品も多分にあり。佐助、才蔵、晴海、団右ヱ門の忍術物、豪傑物の文庫本も多かった。名将としては、幸村、家康、織田よりむしろ秀吉などの名君天下様も現れた。後に、だんだんと西洋物、支那の話、□怪奇なものに変わっていった。 これは5~6年前頃と思ふが、大杉へも傳播したこと爭はないが、後の東中の福井大尉が少尉の頃、大礼服の帽子の鳥の羽根の美しき飾りを見て、ススキの穂を帽子に立てたことを覚えてゐる。子どもの世界の夢だったのであらう。クグツと云ふ罠にて小鳥を捕らへることを盛んにやり、モズを捕らへたり。ツグミもまた多かった。 |
||
| (昭和34、12、12) | ||
 |