
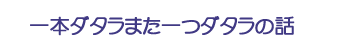
| この怪物については、我は往昔裏面政治、庶民生活に重要なる意義をもつものと思ってゐる。然し、あくまでも雲を掴むやうな傳説的存在である。そして何処までも怪物である。我の知ったところでは、これは相當古く源義経の逃避行のとき、北山、十津川まで彷徨せる時代より継承されしものと考へる。 義経、十津川郷に入りて土民の家に泊まる。人あまたあり。年の老いたるもの、子供に対して、「伯父よ」と呼ぶ。囲炉裏の傍らにありし義経、之を聞きて云ふ。「怪しからぬものなり。」と。辯慶首をふりて考ふ。即ち、これは當時生活上、宅婚、里婚のありしを諷ずものなり。之につき物故せし西川の千葉政清君の書に見ゆ。大台ケ原教会の開祖小森行者も義経のまぐさ刈の鎌を得たりとして始まる。 伯母峯を師走の果ての20日に通るべからず。背に笹生へし義経の馬現る。扨は大台山中に主從して相撲とりたるところありて、今も草も生ぜずなど云ふ。 一本ダタラもかく織りなせしものにして、先づ天ケ瀬(上北山)よりの傳説をあげん。 昔、天ケ瀬に名筒あり。名筒と云ふからに、遥かに年も下りて天文以後のことならん。人ありて山に猟に出る。一本ダタラに出会ひしに、その筒、カラカサを拡げたる如き一本足の怪物に飛びかかりて之を追ひ払へりと云ふ。カラカサは堺市の全盛のとき、つまり松永三好党の跋扈せし室町・戦國末期に入りしものならんため考ふべきなり。 古老に聞く(北山にて)、大きな足跡雪の日に見え、一列に続きたると云ふもの。また、小児の如く小さき跡を唱へるものあり。何れは炉辺の創り話なるべし。然れども色川(那智の裏付近)あたりまでの傳へを総合すると膂力偉大、恐ろしき怪物、一本足にて連峰を前後すると云ふ。而して從者を伴ひたる話なし。我は、ここに疑問あり。(一本ダタラは)必ずこれ政治的に奔馳せし有力なる豪族、山伏なりしに非ずやと考へる。それに狼の項に述べし如く、また地方の豪家を称へるものも之を應用せしなるべし。 中央貴顕、特に皇室發祥の地故に、(熊野)信仰厚く、後鳥羽院の何十度の熊野三山詣の如く、あらゆる月卿雲客も皇室一族、まして一般のものも盛んに三山信仰に來り。藤原秀衡も來たり、和泉式部も來る(その傳説、秀衡桜、式部の逆修の塔と『晴れやらぬ身に浮雲のたなびきて月の障りになるぞ悲しき』の歌あり)。所謂、「蟻の熊野詣で」を現出。権者の保護を受け、いよいよ勢力強大となりし別當まであり(私兵を蓄ふ)。後には政治にも重要なる一役を担ひ、また反するなどしあり(辨慶の父は熊野別當湛海)。徳川時代中期以後も熊野別當は何かの役を幕府より担っていたものと思ふ。なれど文献資料もあまりなし。 只ひとつ、東牟婁郡、今の色川村に住める武士(徳川以前と思ふ)、仮屋刑部左エ門の働きによりて、遂に仕留められ、殺されたりと云ふ。 が、然し、一向限定出來ず。歴史を無視して前後に現れ出でて傳説になってゐる。土俗の傳が洵に不思議にして怪なるはこれなり。實は案外(土俗共)世を律し居たかも知れず、いずれにせよ温存の形とはなり來れるらしい。 一度、昭和5年頃、紀州が生んだ世界的の大天才で努力家の博物学者南方熊楠先生も、我に來りしことありしも、右の如く極めて簡単な答えするより外なかりしなり。 我一度十津川村小原にある宝庫(タカラグラ)の古文書を見るうち「仮屋家証文」を見たり。つまり仮屋家は、十津川村の某所に子孫住むこと間違ひなし。曲事あるべからずのものであった故に、一本ダタラを殺せし仮屋氏は當時有力声望のある家と見えたり。 |
||
| (34、11、25記) | ||
 |