
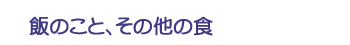
| 幼時の我、天保10年生まれと云ふ浦地の老母に聞きたり。下記の通り、昔は國のブロック別あり。交通も便ならず。まして経済に不利なこの地は、平素にても芋、たふもろこし、アワ、唐きびを喰ひ、山のものも川のものも喰ひ得るものは食したり。いろいろ永き年のうちに、その渋味または毒素を去る方法を考へ出してあり。栃木証文とて栃の木を大切にしたることも、今となりては消え去り、栃木も少なく、見返る人もなしとするも、大事のことなりしなり。唯今はトチモチのみ名をとどむ。その渋の抜き方もコツあるらし。また、我少年時代、北山あたりにては(波抜きした栃の實の)出來たるを粉にして食し易き様にしてありたり。 稗は、十津川重里奥などの外は當地にてはあまりなかりし如し。何としても米少なきの地、山のことなれば、平素は米をほんの少し雑穀に加へるか、暮らしの良いものは夫々、なかなか盆正月くらいしか一般は白米も白餅も得ベ得ざりし如し。 さて、浦地の老母の云ふ(米を得たるときの思想か、尊重の観念よりか)、「一合雑炊、二合お粥、三合あらば飯に炊け」と、通則の如きなりし由なり。 一旦、戦争とか飢饉になると曼珠沙華(オイモチ)の球根を食べしなり。これは、第2次大戦の終わり頃、窮乏せし當時にても(曼珠沙華を)喰べしものなり。我も一度喰べてみたるも、紙を喰ふ如く何の味もなく不味きこと甚だし。味噌などつけて、また焙りなどして食せし如し。樫の實も渋抜きして、いろいろ工夫し、つまり他のものと炊いたり、餅にしたりして食せる如し。 蜜、山芋などは、今にしてみると断然トソプの上々品か上品のものであるだらう。獣肉、鳥類、川魚の如きも珍として、川はトコロ流し、山椒流しで山里の人の今で云ふレクリェーション(但し食生活につながるが)の如くなしたり。獣・鳥の類も、落とし穴、罠、銃猟など全て試み用ひられたり。ススキ(スズキ)追ひのこともレクリェーションと宗教的なこと以外、この間の消息を語る。 米は洵に貴重なるもの。生存の上に希望の火を点ずるものなりしなり。(米は)ただ少ない、ないために食糧上大事絶対のものなりしか分かる。亡父の子供の頃は、麦、ナンバ(たうもろこし)に加へし飯をすくひとりて、仏前に供したるものなり。而して後、これを兄弟して奪ひ合ひせしと云ふ。仏供の、ほんの一口そこそこのものでも此の如し。今の人の生活上よりしては夢の如し。大人はまだしも分かるも、児たちは分かるまひ。折、白米飯、とりどりの山海の珍味、包装の美、たちどころに至る現況では。山の小屋に在るものもポリの袋入りの佃煮、梅干、奈良漬、豆類、肴類、化学的に便なる拒細菌の袋によるハム・ソーセーヂ・バター・ウイスキー、加工せる肴類もなるべく面倒なきものへ發展の今では、その差、夢の如く、驚くべし。(食の豊かさが)普通のこととなり、過去の生活懐古や食の不足、倹約の精神などが忘れられてゐる。然し、考へると人は全智全能でもない。常に制約を鉄の如く確實に受け、大自然の前には足元へも寄り得ぬ。刻々の未來に対して正否の断は不可能、ただ先人の智を頼りて正、良となすのみ。故に機械や文化の發展も一面にては利を生み、反面にては害も甚だあり。眉唾ものなり。人の文化は破滅を招く結果となりはしないか。または他の動物に代はらるるか。昨日の是は今日の非となり、凡てに変はるテンポの速さ。 歯の悪い者多し。脳、心臓、血管、癌、胃腸の病、ヴィタミン欠乏症。病院の治療を法的に受けながら相反する変化の多きこと。理想らしく云ふも、一般は速い高嶺の花なり。敗戦直後とは違ひ、都市は却って得易く多角的なるに、山村では高価、而も医学的に完備せぬ食物は全て横行、都市の商人メーカーの具となるか? 我の考へでは、若し食餌を完璧にせば、恐らくは病も半分に減ると考へる。藥治療、何をおいても基盤の材料となる食餌こそ重大なり。 近時、贅になれて、新宮あたりへ小麦を送り、醤油を作らせる者あり。馬鹿のことなり。『考へる葦なり』と人間につきパスカルは云った。考へると出來る筈である。味噌でもなるベく良い様に醸ることを心掛ければ出來る筈である。事實我も作ったことも過去にある。昔の働く人の話を聞き、その人々の経済や行動、そして肉体を比較すると、今の食物は(黄粉の漬物の果てまで、また先年我の摘発せる天理市の毒菓子の如き)ロにて美味とするも何か不足し、欠くるありて、人体にも影響あるべしと思はれてならない。却って、昔のものにも良きありて、洵に一考を要す。重要の項に属す。問題なり。主食の米にしても、低級はまだしも防虫剤も必要ながら、何かしら炭水化物と化合の状にあるやに思ふなり。 脱線的に記述してしまったが、書留めざるを得ぬ故なり。未來を希望するのみ。絶対と云ふことは、人の世では、なかなか求め得ない。上も下も押しなべて不能。東京の奈良漬、ソーセーヂ、九州の干物を山の人が喰ふ時代であり、土地の人が新宮より野菜を取り(我家も)、百姓の者が南瓜、沢庵を買ふと云ふ時、心すべきことなりと思ふ。 さて、下葛川の福平の祖先(亡父の伯父)、亡父に云ふには、「山造り、子沢山の俺は、菜でも喰ふて、働かねばならぬ。」實際、山を造ったのである。ここでも分かる。次に我の若い頃、玉置川へ往診の帰るさ、徳田の老人と來る途、大きな石塊による積の広い石垣と田の成りしまでの困難を我嘆ぜしに、老人云ふ「中森さん、米の飯喰ふてはこの田は出來なんだよ」と、云ひしことあり。米作る田、この老人の言は、未だ痛く心に残れり。 |
||||
| (34、11、20) | ||||
|
||||
 |