
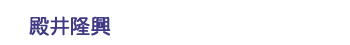
| 少なくとも北越戦爭と云ふ維新の頃の内乱を顧みるとき、その歴史の一片にこの殿井氏の名は永久に現はるるであらう。然も尚我は之を感激すべき訳は此の人、我の有する地、あの向井山に生まれた人であることである。知る人今は数もないであらう。 向井山は、あんな草深い當時としては猪の道の如き通路しかなく、それが木津呂辺まで通じ、船の便も悪く、里人も貧人、見捨てられしやうな九州の果ての孤島くらいに寂しい場所であったに違ひない。また、そこは穀物もあまり穫れず、水さへ不足し碌なことは有り得ず、わづかに四季のうつろひの慰めあるばかりであったらう。 また、殿井氏は宗軒(ソウケン)と云ふ医師の児であるが、よくも生活できたものである。然し、ここで考へられるのは宗軒もただの人でなかったこと、学問のあった人と考へることが出來る。殿井氏が後年、東京で死没するまでのこの人の歴史を知ると自づから分かる。我々は、あの頃あの状態の生活の中からこんな先輩を出してゐたのである。 然らば、果たして今は意志も身体も行動も同人と比して如何。負けてはならない。丁度、軍人の彼でなく、何人でもなり。 北越戦爭嚮導官として、よく戦ひ、功により當時600円を給ひしと記録さる。十津川人は、その頃100入内外戦死してゐる。台湾征伐、西南の役、日清、日露に從軍し、陸軍大佐となり、長寿を得て東京に物故したと云ふ。詳しくは村史にもあり。 今でも向井山に殿井の名の墓あり。戦時中、孫になる人、□隊長が一度訪れしことあり。 大字東中(葛川上流)へ殿井家または家人の中で移轉したることあるか、この地に殿井屋敷あり。肉桂の大木あるところを考へると、医師を業とせるもの、その地に在りしなるべし。 |
||||
| (34、2、28) | ||||
|
||||
 |