
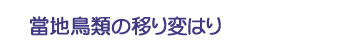
| 耳島山の尾の嶮しき緑の中の枯れ木などに羽端5尺を越えるかと思ふツマブサまで綺麗な毛の生えた鷹がデンと止まってゐたもの。猫も鶏も時々さらはれた。オシドリの群も何百と淵に遊び、その羽音に驚いたもの。雉は鳴き、山鳥の尾を見、ゴイと方言する白い鳥が土穴を掘って巣としてゐたのを知ってゐる。 又、ミズヒョロ(親に不幸した傳説あり)と云ふピンクの鳥もゐた。今は殆ど知れなくなったが啄木鳥(キツツキ)の朝コーラス、そして大小さまざまのツグミ類、シジュウガラ、ツバメに似た鳥の、海の荒れるときに來た。天柱岩の前あたりの断崖にウノス(鵜の巣)と云ふところがある。昔、鵜が來たところと云ふ。 我家の上方40mくらいの高き裏山に「ミズキ」の大なるあり(木理なく下駄などに利用)。小さな赤い實がなると青鳩(アオバト)が多く、それを啄みに來て、平和の声、「アーオー」と鳴きつつ、たくさん來たもの。それを空氣銃などで射ったとしても、なかなか捕れなかった。小学生の頃、クグツと云ふワナを作り、樫の實など入れても捕りにくく、時たま捕ると得意になってゐたもの。20歳の頃、夜道を通ってゐて、捕まへたこともある。(夜盲の例) 犬と猫の脳を見ると、犬が多少脳溝あるに、猫は甚だしく少なく、その馬鹿さ加減と人の云ふことを肯かないこと(つまり無知)が分かる。然るに、あの小さい頭をした脳溝のない「ヤマガラ」が、人の金を受け取ったり、台上にて裏返してたたいたり、これを器に入れ、万国旗を上げたり、祠の戸を開けたりするとは實に自然の法則はうまく神秘なり。 隼は一度見たことあり。片岡八郎の碑の向かふ側であった。矢の如く飛び去ってそれが高速で驚いたもの。啄木鳥(キツツキ)が大胸筋に大なる爪痕を受けて、我家に逃げ込んだことあり。隼は殆ど今は見ぬ。 阿呆どりは、家の近くなどに來り、一ケ所の柴を片付け、土を出しモチを仕掛けると忽ちかかる、最も捕りよい鳥であった。ヒイカツと云ひ、ピョコンとふり鳴く小鳥。モズ。そして川や山辺の反りなどに來た千鳥と云ふもの。ツバクラ、雀(瓦の中に巣をした)も少なくなったやうである。フクロウ、カッコウも減る一方である。メジロは大して変はりないらしい。ウグイスもまだゐるらしい。 ルリ、コマドリの如きは山中深きところに住むが、やはりこれも皆伐が奥へ進むにつれて少なくなるだらう。 ツバメ(ヅバクラ)も少なくなったやうだが、まだちょいちょい來る。 小鳥中の小鳥、ミソサザイも少なくなってゆくやうである。 新宮の河原にあれほど、黒くなるほどゐて入咫ガラスを以て1000年以上も表示され、神威を誇り、誓紙にまで印せられたカラスも今は新宮の河原にも見られなくなった。(まぁー、河原が黒くなるくらいゐたのに) 鳶には二種あったと思ふ。この辺にもヒョービタカと云ふものと鳶(啼き方、前者は啼くが、後者はあまり啼かず)とあり。これも4~5年前は増加して観光客の余しものを喰ってゐたが、昨今は少なくなり、鷹1~2羽と鳶1~2羽の類がいる。 カケスも少なくなった。他の鳥の口眞似をするただ一種の鳥で、鳩より少し小さく、なお細身である。新屋敷のある(子供の頃は山)辺りで、ワナでヒヨドリやツグミも捕らへしこともあったが、今は昔の夢となる。 カワガラス(川烏)と云ふ、苔で岩の間に巣を作る水鳥もあり。巣も捕ったことがある。モズのことを云ふと、4年生の頃、我が友より鷹の落とし子にさも似たよいモズを貰ひ、大きなツグミを与へしに、忽ちのうちに殺して了ひ、小さいくせに之を鋭い爪と嘴で料理して喰ひ、殘ったものを一生懸命になって止まり木の枝の端に突き刺し、ハヤニエを作ってゐるのを見たこともある。女中がタキツケ(焚き付け)として採り來る柴の小枝にトカゲ、カへルのハヤニエがあったのを覚えてゐる。 |
||
| (昭和34年2月20日) | ||
 |