

まず、祭文語り、漫才(三河)、浮かれ節。浪花節は吉田奈良丸が忠臣蔵を出してより全國を風靡したるものなり。我入学の頃(7歳)、最も盛んで義士の浪曲はザラ本または書物となる。小学生の間でも之を眞似てやったものである。女児にも少し流行った。カルタも菓子類も「義士ピエール」ありたり。巴の紋、夜討の装束と輪郭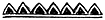 (ギザギザ)など。 (ギザギザ)など。猿廻し、肩に猿を担いで突然やらせる簡易な芸。 デコまわし(これは最近まであった)、エビスの2~3尺の大きさの人形(汚れたいいかげんなものを持って來て)を戸口で舞はす。 「西宮のエビス三郎左エ門殿が、善なる人には福を与へ、ひっくりまっくり雷とエビス様、浮いて來たタイを釣って引っ込んだ」 の如きを唄ふ。後にはあまり來ず。主として漁場の漁夫達が(デコを)担ぐのを利用して、文句も曖昧となり、金色夜叉を唄ったり、ろくでもないことを云って魚をもらったさうである。終戦後もこの歌はよく聞いた。 次に剣舞や手品、三河流を取り入れし旧風の漫才。之は宿に泊まりて行ひ、前記の者は戸口で5分か10分して去ってしまふ。 活動寫眞(エーテル酸素、トリュウムの光源による)もちょいちょい來る。之は然し比較的古い歴史あり。我等5~6歳で、前口上の長い外國物を見たことあり。 この間、亜流の又亜流の自称浪曲師も入り込んで來た。漫才も時折。そして戦時となるや、講談師と云ふ(板橋明善の如く最近までのもの)ものが來るやうになった。競爭もあり、全て時局を取り入れて手振り、顔、聾、□の扮装や器具を加へて人を緊張させたり笑はせたりした。 また、戦時中は、役場あたりの紹介を持って浪曲師も來た。鉱石運搬(何にも役にたたず、國を喰ふ)の兵隊を慰安するとて新宮より芸者、□奴、コトブキの手品も來た。またコマ師も來り、その他いろいろの芸師も(手先の)やって來た。(コマなどは兵士と無関係)終戦後は漫才、浪曲師などいかがわしいものも來た。食糧事情の良くなるにつれ、又生活の波に揺すられて芝居も顔見世廻りをするなど、山に或いは道場に泊まったりして興行したもの。最近もあった。大勢を抱へてやって來るものもある。 映画に変はってから、24年頃より16mm宣伝用のものは役場より來るやうになり、その後新宮の伊藤その他35mmの広角映写など次々に入り込み、時には縄張り爭ひして現時に至る。個人でするものもあり。部落で(上の部落)技師を呼んで映す時もあり、学校も呼びて映すあり。 |
||||||
|
||||||
 |