
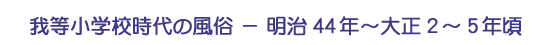
| 涼しき折りはアヤのボタン、時にはガラスボタンを用ひたるシャツー衣のシマや絣の著物に布相當の帯、雨は大抵から傘。サルマタはなし。冬は袷り下にシャツ、メリヤスもありし。何れも筒袖のハンチャと云ふものをかけ、タオルなど頬かむり。教科書は風呂敷にて巻き、斜めに肩に負ふ。一枚手袋、木綿の軍手、しかし、これはあまり甲ひず、懐手。女の児も同様なるも、やや女の児らしく色を添ふ。そして(女の児は)オコシもしたり。弁當は、もう一つの風呂敷にて負ふか、本と一緒に持つ。鞄など稀なり。紅葉の如き手を凍らせて雪と遊んだり、何か話をしたり、度々谷の水を堰き止めたり、春にはフキトウの茎を切り、水車の如く水にかけて遊んだり。 悪戯して柿を採ってみたり、叱られたり、時には魚賣りをからかひて叱られたり、炭焼き小屋に石を投げて(大して意味なし)叱られたり。絶対に女の児とは離れ、それは学校の登校路も然り。女の児をいぢめたり、互いに喧嘩したり、中には障子紙に穴を開けて先生一家を覗いて叱られたりした。 履物は、草履がほとんど。冬、専賣と称する黒、紺のメリケンもの、つま先につきたるを穿ちてはく。雪の日など、特に雪溶けの時は、ベタベタジトジトして冷たくなりしを、そのまま教室にゐるあり。大火鉢にて焙るあり。(父に聞く、後年財をなした東中の島本正男氏は足袋を焼いて泣いてゐたと云ふ)オルガンをさわりたかったものである。 夏は下駄又は下駄の上に草履を打って、冬も履き、雪の日も履き、雨の日も然り。 アケビ、寄生植物のカラスの継ぎ木の實など秋には喰ひしものなり。桜の實の甘いものは勿論、サセンボーの實を喰ったりしてゐた。今でも覚えている「キモトリ」の恐怖心、身近く迫る。根拠なくも人の悪戯声にも驚き、眞顔になって坂道を逃げ、山の中へまくれ込みし女児もありし。学校では体操の外、遊戯は二組に分かれ、グラウンドの相対位置のなるべく離れしところに半円の筋をつけて城として、出でしは互ひに体をたたく。たたかれしは負け、多く殘るは勝ち。そして木材とかを用ひ、ゴリラのやうなる竹の交じる杉林の中に城を作って、遊んだりしたものである。これらは大体男の児の遊びであった。 女の児の遊びにマリツキ(眞綿に糸をかがった毬かゴム毬)。また、手をつないで輪となり、輪の中に目隠しした鬼一人を置き、唱歌を歌ひてグルグル廻り、歌ひ終わりて静止すると、鬼が自分の眞後ろの輪の中の人の名を當てる。名を當てられると鬼に代はると云ふ遊びでオニトリと云った。そのマリツキ歌の中には、かなり昔の文化と云ふか、民俗と云ふもののあることと今思ふ。 〔歌〕 時計が鳴った 起きよ子供よ もう夜が明けた 包み抱へて をくれぬように~ 歌の出發は、主として(田戸の)下より始まる。浦地、そして我。それから(田戸の)上へ、道場(クラブ)の辺りで上へ大声で呼ぶ。出て來る。來ない時は道場に寄って屋根裏で待って(学校へ)行く。忠臣蔵の流行の時、北村信市の提唱で紙に書いた大石親子はじめ義士の名を襟につけて道中討ち入りの眞似をしたものである。 その時分、日露戦争から尾を引きし廢兵院が組織的となり、全國的に紺色の詰襟服とオーバーを着し、帽子もきちんと被った制服姿で藥の入った鞄を肩より下げ、手風琴を鳴らして、「オイッチニの藥を買ひ給へ」など、特に冬の日など、そのエキゾチックな(我々にはそう見えた)歌を長く引いて行くのは風情もあった。 浦地の令兄から送り來たりしとて、我浦地にて初めて森永キャラメルを口にせり。そして直晴氏が兄から送られし『少年世界』と云ふ雑誌あり。珍しく見たものなり。飛行機の初めて登場した頃で、第一次世界大戦のこと多く載り、双六もあり。我も欲しく、遂に『日本少年』を注文しもらひしを覚えてゐる。 弁當の内容は、主として麦飯または米飯。菜は梅干し、タカナ、小魚、。卵や蒲鉾は少なかった。驚くべきは犬コロの頭ほどの握り飯を梅干し(日の丸)で喰ひたり。(焼きたるのもありき。これは飯の質を失せじと親が考へたるか)ナンバや芋の人、又はお粥を絞りとり、粥の米の部分のみをこして詰めたるあり。容器は大抵檜の薄片を曲げて、漆に赤、青を混ぜて塗りたるを用ひ、行李など少なかりき。 昼のお茶の準備は、大抵女児の役目。湯飲を出して最初ついでもらってゐた。 書きたくも、限りなき思ひ出なり。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
 |