
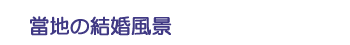
| 今は癈れたるも葛川辺り(當地にては最も早く開けたりと思ふ。役小角と葛婆の語ありせばなり。)では、婚礼の夜、若い衆たちは、ヨイコノその他のめでたい唄を高誦しながら婿の家に(庭のあたり)集まる。父兄は代表して家にゐる。釣瓶さし、酒の容器にめでたき歌を記し、竹竿の端につけて座敷の中へさし出だす。主人はこれを見て、釣瓶に酒を入れてやり、鮓など出して若者に与ふ。若者連は好むところにて、これを喰ひ大騒ぎするなり。又、上葛川辺りは、このほか空の酒樽をさも重たげに梯子を横たへなどし、めでたい歌を唄ひて、徐々にその家の座敷に入り、床の間に据ゑて祝儀を申せしなり。主人挨拶、酒肴を与へれば帰り行くなり。 双方の親達(結婚に)不服の場合、心中するものもあり。式を抜きて二人だけ契りを結ぶものあり。親の心掛け変はりて家に引き取る場合あり。又は家を出でゆくこともある。所謂野合にして妊娠しあること少しとせず。 正式の場合は橋渡しとて某が大体双方の親子娘を得心せしめ、自ら媒酌人たる場合あり。また、媒酌人は別に選ぶ事もある。 この時に(式の前)角樽(ツノタル)と称する漆塗りの樽に酒を入れ、嫁の方へ媒酌人が行き納めて來る。これにて婚約極まる。破談あまりなし。 嫁を連れに行く式の日は、双方ご馳走し、朝までも賑はふ事あり。嫁方へ行くのは媒酌人夫婦(揃いの夫婦)、婿、これに濃い親戚を連れて行く事あり。挨拶を述べ、盛装の嫁出で來たり、家内にて三三九度の盃をなして宴に移る。折りを見て媒酌人は嫁を連れて婿の家に帰る。嫁方からも兄弟姉妹その他從ひて來る。 上座に花嫁、花婿及び媒酌人、從ひ來れる嫁方。次に婿方の人々、祝儀言上の村人集ひ來る。嫁方の挨拶ありて三三九度の盃終わり、集ひし人々全部に流れ渉る。而して夜更けるまで放歌乱舞する。この場合、嫁の方も婿の方も親は直接関与せず、ただ酒肴や礼物などに當たる。引出物と称し、双方より新たなご馳走を各人に配布する。 3日目になると径3、4寸の餅を搗き、眞ん中には紅にて丸く恰も日の丸の如きを作り、新夫婦揃って親戚や近所を廻り、挨拶して餅を配るなり。俗に三日帰りと云ふ。 三重県五郷村方面は今は滅びしも、その行列の途中、村人金品をねだりしと云ふ。菅家、家の娘嫁にゆく際、亡父が宰領たり、金銭をとられしよし。少なしとて後追ひかけ、又とられしと云ふ。 |
||||
|
||||
 |