
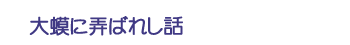
| 下葛川の某(時は明治5年頃)、玉置山からの帰途、里近くの小原谷まで來る時、恰も黄昏に近し。雨上がりの道、ふと見ると道の眞ん中に2尺以上の大蟆悠然と控へゐたり。仰天せしも、落ち着く心と共に悪戯を試みたり。氣を取り直して携ふるところの杖にて、いきなり蟆の背を殴りつけたり。然るにその蟆はピョイと一間余り上り道へ跳び、自然体のままなり。そこで同人は寄り道して、もう一つ殴ったのであるが、またまた前方へ跳ぶ。さて、それから氣が変になり、これを繰り返すこと頻り、遂には片岡八郎の碑の辺りまで追ひて行く。蟆はいつしか姿を消したるも半狂乱となり、山包丁を抜きブンブン振り廻して上り來る。丁度折節、大字竹筒の某、石垣に腰を下ろして休みゐたり。これを見、驚き、さては氣狂か、又は何かにより精神錯乱せしにやと思ひ、幸ひ面識あるため、「お前何と云ふ馬鹿な眞似をするのか。何も居らぬではないか。しっかりせい。」と、怒鳴り付けしに顔面蒼白の同人は耳を貸さばこそ。いきなり、「おのれこそ、俺の知る人に化けたるに相違なし。」と、その男に切り付けたり。迷惑千万の竹筒人は、右に左に身をかはし、大声にて怒鳴り、漸くにして鎮静するを得たり。 後で、その男は云ふ。「ああ、俺は如何したことか、あの時に杖の一打せなんだら良かったのである。徐々に神氣朦朧となり、洵にすまぬことをした。」とて彼に平謝りせしと云ふ。 現在(昭31、6、10)では、こんな話も形勢が変わり、殆ど話がない。やはり文化の進展は否み難い。 但し、今もって狐憑きやへんてこなマジナイ、曲解された弘法大師等々、てっとり早いインチキ又はイカサマの以て非なる信心は、なほ殘る。外國に比べ小百年もこの面では遅れてゐるのではないか。教義や信仰を押しつけることもあまり感心出來ないが、人を非常不明にすることは間違ひないと思ふ。 |
||||||
| (昭31、6、11) | ||||||
|
||||||
 |