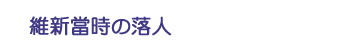|
|
|
|
| |
この頃の特徴は、落人と云ふも、大体学者(世に容れられざる)又は、医師(学者と通ず)の落人多く來たりて、中には尾羽打枯した乞食同然のものもあり。例えば、葛川島本盛吉老医の父(義理の父)たる石川玄龍の如き、又玉置川の正式なる医師玉置英隆氏の父の如き。然しこれは天職であるが故に、鄙びた當地にては要望されて土着せしなり。
単なる学者のみでは生活にも窮し、寺子屋式の仕事よりなし。然るに感心すべきは武蔵より來れる高橋管次と云ふ学者、本家の与平治老の肝入りにて後妻も貰ひやり、弟子として東辰二郎、友吉外杉岡直吉、東藤二郎など教へを受けたり。有ったとて貧乏暇なしの折り、我が祖父はその頃已に山にてコッパタにケシズミにてローマ字を稽古、米入れる袋なく、バッチの端を括り之に代ゆなどの折、又与平治も頑固一遍の老人なりて一番広い麦畑、14歳で唯一人打ち、振り返へれば、初め蒔きたる麦青々してゐたりと云ふ。その他貧にまつはる話、数々。仏の御供(麦飯の内より僅かにとる)の飯を父ら子供のころ取り合ひしたりと云ふ所において、此の学者(哀れむべき)を世話し、苦にゐても教育の事を考へし如き、昔の人と雖も単に片付け難き一種不滅の哲理さへ窺ひ知ることが出來る。現に上田の墓には弟子どもの建てし一基の墓碑あり。又、苦しき生活の内にも昔の人は努めて余裕ある人生、落ち着いた人情を考へしものか。今に上田には浄瑠璃三味線ありたり。そして台本もありたり。人集ひて之を樂しみ、人生樂しみ得たに違ひなし。尚、納屋の屑箱を調ベるに、我の祖父、曾祖父、大叔父などの歌、文字、繪の事、作文など實に多く見る。特に明治20何年に死せし勘三郎は、よほどリーダー一巻欲しかりと見え、やっと望み叶ふや、「我この書物を得んとすること久し。今漸くにして入手するを得たり。この嬉しさ、何にたとふべき。手の舞ひ、足の踏む所をしらず」と、あり。現在の賣り喰ひと不勉強と小さな個人的なコスイ考へよりない、能のないくせに私利のみ窺ふだけの人間、文明の利器を求むるにも祖先の山にて購ふて恬然たり。人には誠意なく口先のみ、見下げ又は乞ふと云ふ、むしろ退嬰的である。
何故に現代人たらんとせば、之に時流の波にのり、ついて行かぬか。勿論、本質の質、好悪により進歩的に事業家で巨富を目指してもよし、又縁の下の力持ちたる貧乏学者でもよろしい。意義あれかしと思ふ。 |
|
|
|
|
|
| 注- |
・(84)話は、「維新當時の落人」となっているが、別の話が加わっていると考えられる。話の筋が途中から変わってしまっている。 |
|
・上田-中森本家 |
|
・勘三郎-瀞八郎の祖父福重(陳平)氏の次々弟 |
|
|
|
|
|
|
|