
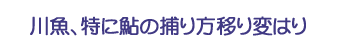
| まず、古い方から云へば、「ヤナ」を懸ける。網を打つ。この間に毒流しあり。爆薬使用も。その後、テングスやいろいろ知識の向上につれ、陸上または舟上から鮎をカケル方法、つまり、オトリを捕らへ眼の部分と尾の部分に釣鍼にて糸を通じ、尾の部に相反する釣鍼を仕事、糸を経て釣竿を動かし、水中を誘導せしむ。他の鮎は、良き仲間と早合点して之にザレて來るうちに,遂に尾部の釣鍼にかかると云ふ訳。釣り師は、元氣なきこの鮎と取り替へ又同断。これは大して捕れぬが、大きいのがかかり、趣味もある。 毒流し(巴豆、生石灰、山椒の皮、トコロ、クルミ、最近は農薬ゲラン、特に名高い青酸カリ)は、禁ぜられ、密漁の形となり、主としてCNが使用され、現今も絶えない。又、爆薬物、ダイナマイトを第一にし、いろいろあり。危険も多く、不具になったりする者少々あり。警察も全力を尽くすようでもない。余の考へるにCNやダイナマイトの如きは、甚だ不都合なりと思ふ。第一、拾へない無盡の殺生をする。緋鯉又は大鯉など一發で大量獲得され、段々少なく、余の幼時よりは形も半分になってしまった。簗は、古代より用ひられし方法なるも、季節と大がかりの装置、天候に関し、之は許可を要する。然し出水時にうまく合致せば、實にすばらしい捕獲あり。足元へ何百何千飛び上がり來る。塩・味噌・酒を用意して、舌つづみをたらふく打つ者あり。實に独特の気分で、鮎に氣の毒な位である。余も2回あまりこの経験あり。舟に3杯あまり、處置にも窮すると云ったところ。猫も見向きもしない。然るに万が一、材木の如き大きな害物が流れ入り、大怪我することあり。又、水都合その他にて1日僅か1、2尾にて終わることあり。賭に等しい。 然るに余の少年時代、正當な方法は上記友掛け、網打ち(これは然しなかなか技術を要す)が重なりしが(而して、その時分は魚も多かったのである)、余、9歳か10歳の頃より糸端に直接鍼を付して、直接引き掛けんと云ふ傾向が出て來たのである。乃ち釣り糸の端にスバル形の(稍大き目のものあり)ものを装着して、尚、鉛の玉を加へ錘として鮎が岩の珪藻を喰べんとして來るを傍らに沈ませをきし鍼もて引掛けるなり。 然て、この方も成績良からず、木箱(大きさ1尺もあれば大)の一端にガラスをはめ、平行光線として川底を眺め、瞭然たる魚の姿を視て、小さな細身の銛で突きとること始まるに至る。まもなく竹竿の先端の細い部分に釣鍼を取り付け(ゴム紐など用ふるあり、かかれば鍼はずれて糸に余裕を持たすなどの工夫し)直接、主として錨を入れし舟より群れを睨んで引っ掛ける事始まりぬ。最初は大した流行もなかりしに、愈々遂日盛んとなり、鵜より酷いと云はれ、昨今は9割9分まではこれなり。故に縣によりては、特に条例をもうけ、之を(水鏡と併用)禁止せるあり。然し表面のことにて、その盛んなること、今は只これによるのみなり。 右以前、フリカケと称し、暗夜、淵の辺りに淵網と云ふ大いなる網を以て取り巻き囲み、突然ムギワラなどに点火して振りまはす。驚きたる鮎は、忽ちにして網にかかってしまふ。多くは大量を得るなり。 又、最近、或る特定の場所にては、科学知識を利用し、これをとるものあり。特定の場所とは、發電所に多し。水車の中へ多量の空氣を交ぜて放出すると、水は乳白色となる。空氣の微粒子の多く含める水中にては魚も呼吸不全となり、遂には死するものなり。然し、かかることをすれば、水車は非常に酸化を受けてよろしからぬよしなり。 結局、チョンガケと云ふ水鏡を利用しての直接法は、鵜よりも或いは之に匹敵すべし。故に法律で取りしまられる。 天はよくしたもので、アメノウオの如く珍味なる魚は、ほとんど山の奥底まで住んでゐる。7、8寸位は一番佳なり。大は1尺2、3寸、又は以上もあり。恰も鯖の大きさの如し。鮎の如く下流へ下り産卵せず。己が住む淵の辺りに卵を産みつくるなり。歯は鋭にして、他の魚或いは虫の顆まで食する。青々せる奥山の黒き淵にユラユラするのを見ると氣味が悪くなって來る。 里人の傳へに木の柴より発生すると云ふムツと称する3、4寸位の魚も山奥の谷に見られる。ミソガラ、糠なりを入れし瓶又は一種の籠を水中に投じておけば多くとる事が出來る。焙って醤油をつけ喰ふにガサガサして、あまり珍ならず。されど奥山の事、余、一度喰ひしに、その時はうまかったのである。この魚は、割合に人を恐れず、例へば蓬の根に引き結びを作り、水の上から下して括ることも出來、子供の遊び相手なり。 約12、3年前より、鱒科のアメマスと云ふ味はやや劣るが大いなるアメノウオに似たる魚、北山あたりで放ちしや、大分増殖しあり。又、方言「ハイ」に似たるも薄青赤の4、5寸の魚も出で來る。 又、アメノウオなどは、洪水を予知するのか、その期、迫れば砂を喰ひて体重の増加を計るよしなり。丁度、これに限らず、他の魚にもあらん。 |
||||||||||
| 30、2、28 | ||||||||||
| 鮎は、ザレルよりも縄張りを爭ふものならんか。 | ||||||||||
|
||||||||||
 |