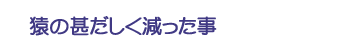|
|
|
|
| |
余の少年時代は、猿の生息は實に夥しきものであった。先づ、現在の大川の辺り、山彦橋の向かふの山あたり、小川の局の前の山あたり、見張りの猿を王として、大群小群がバラバラしてゐた。人が川で魚を採ってゐると、怒って木をガサガサし、鳴き声たてて揺すったりしたものである。銃を持ってをるとよく知ってをり、なかなか現はれない。そして逃げ足も早い。追ひたててみる。大声で。すると木から木へ飛んで逃げるのであるが、子猿を母猿が背負ひて飛ぶ様を見、大いに感心させられたものである。又、一匹猿と称して、我幼時、舟着き場前の岩へ出て來て、船夫が板など荷積してゐるにもかかはらず、平氣で寝てゐたりしたもので、終いにのそのそと5歳の子供位の奴が岩を登って山へ帰ったものである。又、有名な某画伯が來たときに、下瀞の辷り岩下手の所で猿が水を呑んでゐるのを見附け、手にしてゐた柿を投げ与へたところ、上手に手で受けとめたと云ふ。 |
|
|
|
|
|
| 注- |
・小川の局-現在の瀞郵便局のことで、北山川を大川(オオカワ)と称するに対し、葛川を小川(コカワ)と呼んだ。
なお、猿は山彦橋の向かいあたりに今でも、ちょいちょい出て來る。猿のことをエンコ、エテコ、時には「山のワカイシ」と呼ぶ人もある。 |
|
|
|
|
|
|
|