
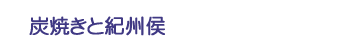
| 昔は、炭焼きの事を呼ぶに、この言葉の上に「御」の字を付けて「御炭タキ」と云った。紀州侯の産業政策の現はれであり、保護したものである。 事實、他の仕事、この非文明の地においてもすっかり変はってしまったが、炭の事だけは仮令改良ガマとか何とかが發明されても、採算の上から技術の上からやはり昔の方式である。 窯の上、後方の排氣孔は、普、弘法大師に教へられたと云ふ。尚、余の小学生時代には、その分類法は全く細密を極め、10何程もあったと記憶している。 昔は、ワイヤーを使ふ事を知らず、投げ下し、持ち運びを主としたるに付、可驚懸崖の上に遠くから土を運び、窯を築き、己の住居とするは一疊にも足らざるところあり。岩穴を利用したりしてゐる。そして相當広面積を有する仕事場、大地と接するは僅か三尺にも足るか足らざるか。他は貮參間の広さに「ユカドコ」と称して、崖下の立木の叉などを利用して木を横たへなどして並べたる木の上に土を盛りて作ったりした。これは今でも栃谷山で見る事が出來る。恰も南洋のボルネオなどでやるダイヤ族の屋に等しい。 然し今では昔より窯は大分大きくなり、木炭も昔の倍以上、即ち100俵位出せるよう作ってある。小屋も良くなってゐる。昔は、こんなのを時々移轉しては築造したものである。よくも生活に堪へたものである。考ふるに、これらの人々は土人や蕃人とあまり違はぬ。却って不自由な生活をして、文化と云ふものよりよほど遠かったにちがひない。 日清戦争の歌に『四千万の国民は』と云ふ文句があるが、徳川時代以前から十津川はあったのである。何故他に土地を求めて開墾しなかったものか、疑問であるが、理由もある。結局のところ、落武者が理由あって、不自由の生活に甘んじたのであらう。無年貢なれば年貢のいらない事、領主より苛歛なる貢求を受けなかった事など原因であろう。 然し、極めて安い製品を肩に汗してよくも持ち出し、羊腸の道路、それも険しきを運んで勘定に合ったものであると感ずる次第である。 自分も小学校の頃、約一里離れた五平谷より炭を持った事(「持って見よ」、と父より云はれ)を覚えてゐる。 |
||||||||||
|
||||||||||
 |