
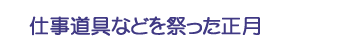
| 我々の子供の頃、正月には神棚の事は勿論なるも、山働きの家では、斧や鋸、鉈などを清め、榊を供へて祭ったものである。封建的と云ひ去るべくあまりに正月らしかった。又、舟も水の源も注連縄、榊、小さな餅のキレなど供えて祭ったものであるが、段々廢れてしまった。 浦地の祖母などから聞いたには、その若い頃(この祖母は天保9年生まれ)、正月、玄関に人が來たり、「モーモー」と声を掛けると、家の人が「ドーレ」と云ひ出で來て招じ入れたと云ふ。 世の中は、すっかり変はってしまひ、氣分つまり昔あった正月の独特の氣分もすっかりなくなった。 |
||||||
|
||||||
 |