
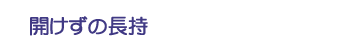
| 昔と云っても、天保の頃を少し登った頃と思ふ。小松の下にある、現在の下瀧に大きな問屋があった。これが現在の西山村の山本と云ふ財産家と田戸浦地へ分かれたと云ふ。ここに開けずの長持と云ふ大長持があって、平常は絶対見るを許さず。家の重大事に際して開けよ、との傳へがあった。あるとき家運も傾き、いよいよ重大事に際したるため、子孫等寄り集まり協議の末、開けて見た。すると松の一重オコが出てきた。何か大判小判でもザクザク出てくるのかと思ふと、担い棒がたった一本出てきたのである。人々は茫然とした。しかし、考へてみると祖先なる人の意味はこうである。謎を解くと、祖先は裸一貫で天秤棒を担ひ、塩売りをして儲け出した人である。即ち、この心地で巻き直しで働け、とのことである。面白い話である。 | ||
| 注-・山本-小松の下流、対岸の和田にあり。 ・下瀧-有蔵の東、国境の少し上、小森ダムの放水路工事まで家が二・三軒あった。 ・松の木の一重オコ-松の木の梢に近く、クルマ(枝の岐れ目)とクルマとの間の部分で作ったオコ(天秤棒)のことで、これだけの松はなかなかないものだ。爪がなく刈草などを刺して運ぶ棒はサソと言う。 (この紙、戦争中のものとて不良故にこの如し。XよりXへの如く、次ページを飛び、第三ページへ移るものもあり、又順序よく記すものもあり。) 注-上記のとおりノートの紙質が悪いため、たびたび一ページとばしてXなどで連絡しているが、飛ばしたページへ、その後鉛筆などで別の話を記しており、記述年代不明のものが多い。 |
||
 |